日がまだ傾く前に降り出した雨の為、整備が思うように捗らず、クーパーは苛々していた。にわか雨にしては雨脚
が速く、あっという間に服の中まで、したたか濡れた。驟雨が連れて来た一足早い夕闇は、既に辺りを濃く包んでい
る。キャップの先からぽたぽた雫が垂れるのを、クーパーは忌々しそうに眺めてから、くそっ、と吐き捨てて濡れない
ようにヘリの下に置いてあった工具箱の蓋を閉め、脇に抱えた。止めだ、止めだ。そう誰に言うわけでもなく毒づい
て、作業を終わらせることに決めたのだった。
が速く、あっという間に服の中まで、したたか濡れた。驟雨が連れて来た一足早い夕闇は、既に辺りを濃く包んでい
る。キャップの先からぽたぽた雫が垂れるのを、クーパーは忌々しそうに眺めてから、くそっ、と吐き捨てて濡れない
ようにヘリの下に置いてあった工具箱の蓋を閉め、脇に抱えた。止めだ、止めだ。そう誰に言うわけでもなく毒づい
て、作業を終わらせることに決めたのだった。
ほぼずぶぬれになって詰め所に飛び込んだクーパーは、いきなり顔面にタオルを投げつけられ、咄嗟にそれを受け
止め、何だと飛んできた方を見やれば、空きデスクに凭れたドゲットがいた。ドゲットは、クーパーがタオルを受け止め
たのを確認すると、黙ってコーヒーメーカーの前に向かう。クーパーは、タオルを首に巻き、工具箱をロッカーに閉まっ
てから、キャップをデスクに放り濡れたジャケットをコート掛けにかけると、どさりと椅子に腰を下ろした。
止め、何だと飛んできた方を見やれば、空きデスクに凭れたドゲットがいた。ドゲットは、クーパーがタオルを受け止め
たのを確認すると、黙ってコーヒーメーカーの前に向かう。クーパーは、タオルを首に巻き、工具箱をロッカーに閉まっ
てから、キャップをデスクに放り濡れたジャケットをコート掛けにかけると、どさりと椅子に腰を下ろした。
ごしごしとタオルで髪を拭くクーパーの目の前に、湯気の立つマグカップが差し出され、眼を上げればドゲットが自
分もカップを手に、立っている。クーパーは入れたてのコーヒーを上手そうに一口啜ると、ドゲットを見上げた。
分もカップを手に、立っている。クーパーは入れたてのコーヒーを上手そうに一口啜ると、ドゲットを見上げた。
「何時来たんだ。」
「ああ・・うん。」
「それじゃ、分からんぞ。何時なんだ。」
「さっきだ。」
素っ気無く答えたドゲットは、クーパーが寒そうに肩を縮込ませているのに気付き、マグカップをデスクに置くと、部屋
の隅からオイルヒーターを引っ張ってきて、クーパーの直ぐ前に置きスイッチを入れた。
の隅からオイルヒーターを引っ張ってきて、クーパーの直ぐ前に置きスイッチを入れた。
「お、悪ぃな。」
そう言ってクーパーは、ヒーターの温度を最大に上げ、身体を前かがみにして近づけると、マグカップを両手で持ち、
ちびちびとコーヒーを啜る。程なくヒーターの効果が現れ始め、クーパーの身体から、湯気が立ち始めた。するとよう
やく身体も温まり、人心地付いたクーパーは、そこで初めてドゲットに注意を向けた。
ちびちびとコーヒーを啜る。程なくヒーターの効果が現れ始め、クーパーの身体から、湯気が立ち始めた。するとよう
やく身体も温まり、人心地付いたクーパーは、そこで初めてドゲットに注意を向けた。
ドゲットは、オイルヒーターを挟んだ向こう側に、椅子を持ってきて長々と足を伸ばして座っている。そのまま黙って
椅子の背に凭れ、片手にマグカップを持ち、真正面の窓の外を眺めていた。
椅子の背に凭れ、片手にマグカップを持ち、真正面の窓の外を眺めていた。
クーパーは、そんなドゲットを眺めながら、不思議な生き物を見るような気分に囚われた。恐らくこの男は、クーパー
の知る人間の中で、一番分かり易く且つ又一番分かり難い男かも知れないからだ。自分が話しかけなければ、ずっ
と黙ったままいるであろうこの男の横顔をちらちらと盗み見ながら、クーパーは5年前初めてドゲットと会った頃のこと
を思い出していた。
の知る人間の中で、一番分かり易く且つ又一番分かり難い男かも知れないからだ。自分が話しかけなければ、ずっ
と黙ったままいるであろうこの男の横顔をちらちらと盗み見ながら、クーパーは5年前初めてドゲットと会った頃のこと
を思い出していた。
その夜、当直だったクーパーは、ヘリの整備をしていたが、人の気配を感じて、ひとしきり辺りを見回った。すると、
その気配が電圧室の上からするものと突き止め、何だろうと確認の為上ってみると、そこにいたのがドゲットだったの
だ。クーパーは胡散臭そうに、じろじろとドゲットを見ながら、乱暴な口調で詰め寄った。
その気配が電圧室の上からするものと突き止め、何だろうと確認の為上ってみると、そこにいたのがドゲットだったの
だ。クーパーは胡散臭そうに、じろじろとドゲットを見ながら、乱暴な口調で詰め寄った。
「見かけん顔だな。誰だ。お前。」
「先月、入局したジョン・ドゲットです。よろしく。」
立ち上がって差し出された手を無視し、ドゲットの胸に下がる身分証をちらりと見て、クーパーは不機嫌に答えた。
「パイロットのケネス・クーパーだ。こんなところで何してるんだ?」
「考え事です。」
「考え事?なんだそりゃ。」
「まあ、色々と。」
「そんなもん、自分のオフィスでしろ。」
「ああ、そうですね。」
「分かったら、さっさと降りろ。ここを、お前等みたいな人間にうろつかれるのは、目障りだ。」
「分かりました。」
ドゲットはあっさりとそう言って頷いた。そして、二度と顔見せるんじゃないぞという雰囲気で、仁王立ちするクーパー
に、失礼しました、と言って帰って行ったのだ。その時は突然の闖入者を体よく追い払い、高笑いしたのはクーパーだ
った。
に、失礼しました、と言って帰って行ったのだ。その時は突然の闖入者を体よく追い払い、高笑いしたのはクーパーだ
った。
しかし、その男はそれから2日後に又現れた。電圧室から降りてくるドゲットを見咎めたクーパーは血相変えて、男
の前に駆け寄った。
の前に駆け寄った。
「ドゲットって言ったな。お前。何やってんだ。」
「ああ、こんばんわ。」
「こんばんわじゃない。ここで、何をやってるか聞いてるんだ。」
「この前と同じですよ。」
「あぁ?お前、俺の言うことを聞いてなかったのか?」
「いえ、窺いました。」
「じゃあ、何で来たんだ。」
「さあ。」
「さあ?さあって何だ。目障りだから、来るなって言ったんだぞ。」
「今夜は、いらっしゃらなかったようだったので・・・。」
「減らず口を叩くな。俺がいてもいなくても、用が無ければここには上がって来るな。分かったか。」
「分かりました。」
ドゲットは再び同じように、あっさりと引き下がった。エレベーターへと向かうドゲットの後姿に、もう絶対来るんじゃな
いぞ、と怒鳴れば、後ろを向いたまま、黙って片手を上げて去っていった。これだけ言えばもう来ないだろうと、クーパ
ーは邪魔者を追っ払ってせいせいした気分で仕事に戻り、ドゲットのことなど直ぐに忘れてしまった。
いぞ、と怒鳴れば、後ろを向いたまま、黙って片手を上げて去っていった。これだけ言えばもう来ないだろうと、クーパ
ーは邪魔者を追っ払ってせいせいした気分で仕事に戻り、ドゲットのことなど直ぐに忘れてしまった。
ところが、それから一週間もしないうちに、同じことが起こった。仕事に掛かろうとしたクーパーは嫌な予感がしたの
で、まさかと疑いながら電圧室の上に上れば、予感は見事に的中する。そこには最初に会った時と同じ場所に腰掛
け、じっと夜景を眺めるドゲットがいた。ドゲットはクーパーが眼の前に立つと、激怒し顔を真っ赤にしているクーパー
の顔を平然と見上げ、こんばんわ、などと挨拶をする。クーパーは頭が沸騰し始めた。
で、まさかと疑いながら電圧室の上に上れば、予感は見事に的中する。そこには最初に会った時と同じ場所に腰掛
け、じっと夜景を眺めるドゲットがいた。ドゲットはクーパーが眼の前に立つと、激怒し顔を真っ赤にしているクーパー
の顔を平然と見上げ、こんばんわ、などと挨拶をする。クーパーは頭が沸騰し始めた。
「ドゲットお前一体どういうつもりだ!?」
「何がです?」
「あれほど言ったのに、何故来るんだ!?」
「ああ、今日はこれを届けに。」
ドゲットはスーツの内ポケットから書類を取り出すと、クーパーに差し出した。怒りが収まらないクーパーはそれを引っ
手繰ると、ドゲットを横目で睨みつけながら、素早く眼を通す。すると、ドゲットは立ち上がって、言った。
手繰ると、ドゲットを横目で睨みつけながら、素早く眼を通す。すると、ドゲットは立ち上がって、言った。
「じゃあ、確かに渡したので、帰ります。」
「待てよ。こりゃ、燃料の明細書だ。なんでお前がこんなもの届けるんだ。」
「ついでがあったもので。」
「ついで?経理のねえちゃんは、どうしたんだ。」
すると、ドゲットは肩を竦め、さあ、とのんびりとした口調で答え、何事も無かったかのように電圧室を降りてゆく。慌て
たクーパーが後を追いかけ、エレベーターの前でようやくドゲットを捕まえた。
たクーパーが後を追いかけ、エレベーターの前でようやくドゲットを捕まえた。
「いいか。こういうものは、詰め所に置いとけばいいんだ。詰め所の俺のデスクに置いたら、俺がいてもいなくても、と
っととここから消えろ。二度とここに顔出すんじゃないぞ。分かったな。」
っととここから消えろ。二度とここに顔出すんじゃないぞ。分かったな。」
「分かりました。」
ドゲットは神妙な顔付きでそう答えると、エレベーターに消えた。後に残ったクーパーは、憤懣やる方無いといった風
情で歯噛みしていた。何なんだ。あの男は?この俺に三度も同じことをするなんて、信じられん。新手の嫌がらせ
か?クーパーは明細書を握ったまま足音高く詰め所に戻りながら、顔を顰めた。
情で歯噛みしていた。何なんだ。あの男は?この俺に三度も同じことをするなんて、信じられん。新手の嫌がらせ
か?クーパーは明細書を握ったまま足音高く詰め所に戻りながら、顔を顰めた。
この場所は、言わばクーパーの城だ。パイロットの聖域なのだ。どんな肩書きの人間でも、自分がいなければ、ヘリ
は飛ばせない。自分がシフトの時、ヘリポートの王様はケネス・クーパーなのだ。しかも、FBI専属パイロットの中で、
自分が一番キャリアが長く、操縦の腕は、他の追随を許さない。誰しもクーパーには一目置いていたし、ここでクーパ
ーに逆らうような真似は、いざ自分がヘリを要請した時に、とんでもないしっぺ返しを食らうと評判だったので、誰もし
たことが無い。
は飛ばせない。自分がシフトの時、ヘリポートの王様はケネス・クーパーなのだ。しかも、FBI専属パイロットの中で、
自分が一番キャリアが長く、操縦の腕は、他の追随を許さない。誰しもクーパーには一目置いていたし、ここでクーパ
ーに逆らうような真似は、いざ自分がヘリを要請した時に、とんでもないしっぺ返しを食らうと評判だったので、誰もし
たことが無い。
それなのに、何だ。クーパーは乱暴にドアを閉め、どっかと椅子に腰掛け、腕を組んだ。勿論頭の中はドゲットのこ
とで一杯だ。あの人を食った返答の仕方は、どういうつもりだ?馬鹿にしてるのか?先月入局したと言っていたな。ま
だ俺の噂を知らんのか?だがその時、ふと先月ヘリを飛ばした時、数人の捜査官に混ざってドゲットがいたことを思
い出し、それじゃあ、そんなはずはないか、と首を振った。何せあの時同乗したのは、クーパーでさえ知っているほ
ど、噂好きな捜査官達だった。あの連中が話さないわけがない。
とで一杯だ。あの人を食った返答の仕方は、どういうつもりだ?馬鹿にしてるのか?先月入局したと言っていたな。ま
だ俺の噂を知らんのか?だがその時、ふと先月ヘリを飛ばした時、数人の捜査官に混ざってドゲットがいたことを思
い出し、それじゃあ、そんなはずはないか、と首を振った。何せあの時同乗したのは、クーパーでさえ知っているほ
ど、噂好きな捜査官達だった。あの連中が話さないわけがない。
そこで、クーパーはあることに思い当たった。ドゲットとは、あの夜電圧室の上で会った時が、初対面じゃ無い。その
少し前に自分がヘリに乗せているのだ。確かに自分は、ヘリに乗せる人間なんか一々眼を配っちゃいない。しかし、
ドゲットはどこをどう見ても、人目を引くタイプだ。決して派手ではないが端整な容貌や、醸し出す雰囲気などに、妙に
重みがある。それなのに、何故覚えていなかったのだろう。そういえばあの時奴は目的地に付くまで、殆ど何も喋ら
なかった。他の捜査官に話しかけられても、短く答えるだけだ。ヘリに乗ってからは、完璧に自分の気配を消していた
な。それでか。
少し前に自分がヘリに乗せているのだ。確かに自分は、ヘリに乗せる人間なんか一々眼を配っちゃいない。しかし、
ドゲットはどこをどう見ても、人目を引くタイプだ。決して派手ではないが端整な容貌や、醸し出す雰囲気などに、妙に
重みがある。それなのに、何故覚えていなかったのだろう。そういえばあの時奴は目的地に付くまで、殆ど何も喋ら
なかった。他の捜査官に話しかけられても、短く答えるだけだ。ヘリに乗ってからは、完璧に自分の気配を消していた
な。それでか。
クーパーは、あの野郎。と唸った。それならそうと何故あの時言わないのだ。むかつく野郎だ。クーパーは、この職
に落ち着くまでに培った苦難な人生経験から、些か捻じ曲がった性格になっていた。従って、彼に掛かれば殆どどん
な人間も、むかつく野郎なのだが、その中でも特に嫌いな人種が、肩書きをひけらかすエリート意識丸出しの役人な
のだった。とはいえ、彼自身がそういった連中の真っ只中で仕事することには、何の抵抗も無い。むしろ、大嫌いな彼
らを睥睨出来ることで、屈折した喜びを見出している偏屈な男だった。しかも、クーパー自身それを認め、隠そうともし
ないのだ。これでは、周りから煙たがられても、致し方ない。
に落ち着くまでに培った苦難な人生経験から、些か捻じ曲がった性格になっていた。従って、彼に掛かれば殆どどん
な人間も、むかつく野郎なのだが、その中でも特に嫌いな人種が、肩書きをひけらかすエリート意識丸出しの役人な
のだった。とはいえ、彼自身がそういった連中の真っ只中で仕事することには、何の抵抗も無い。むしろ、大嫌いな彼
らを睥睨出来ることで、屈折した喜びを見出している偏屈な男だった。しかも、クーパー自身それを認め、隠そうともし
ないのだ。これでは、周りから煙たがられても、致し方ない。
勿論、クーパーにしてみれば、FBIの捜査官や職員が自分を煙たがっていることなど、先刻承知でむしろその事を歓
迎していた。何時の頃からか彼は、心底孤独を愛する男になっていた。この場所にいて、ヘリを操縦することが出来
れば、人付き合いはなるべく避け、煩わしいことは乱暴に退ける。それが、今現在のクーパーが最も最適な生活を築
く基盤だった。
迎していた。何時の頃からか彼は、心底孤独を愛する男になっていた。この場所にいて、ヘリを操縦することが出来
れば、人付き合いはなるべく避け、煩わしいことは乱暴に退ける。それが、今現在のクーパーが最も最適な生活を築
く基盤だった。
ところが、それが通用しない男が現れたかも知れないのだ。クーパーは、内心焦っていた。ドゲットという男が、どう
にも理解し難い。忌々しげに舌打ちすると、クーパーは握り締めていた、明細書を丸めて壁に投げつけ、力任せにデ
スクに拳を打ちつけると、呟いた。
にも理解し難い。忌々しげに舌打ちすると、クーパーは握り締めていた、明細書を丸めて壁に投げつけ、力任せにデ
スクに拳を打ちつけると、呟いた。
「くそ。苛付く男だ。今度会ったら・・」
今度会ったら、何だと言うのだろう。クーパーは、その先が思い浮かばず、そんな自分に舌打ちし、デスクの上にある
ものを乱暴に払い落とした。
ものを乱暴に払い落とした。
ところがクーパーが、ドゲットに会ったらどうするのか思いつかないうちに、事態は思わぬ方向に進んでゆく。それか
ら何度か大きな事件が重なり、ヘリの出動要請がある度にドゲットと顔を会わせることになったのだ。クーパーはこの
時とばかりに、隙あらばドゲットの足を掬おうと、彼の一挙一動を観察した。その時まだクーパーは、自分に接したド
ゲットの態度から、よほどの能無しか、鈍感で無神経な男かと決めてかかっていた。だが、何度か行動を共にするう
ち、それがとんでもない勘違いだと気付いた。
ら何度か大きな事件が重なり、ヘリの出動要請がある度にドゲットと顔を会わせることになったのだ。クーパーはこの
時とばかりに、隙あらばドゲットの足を掬おうと、彼の一挙一動を観察した。その時まだクーパーは、自分に接したド
ゲットの態度から、よほどの能無しか、鈍感で無神経な男かと決めてかかっていた。だが、何度か行動を共にするう
ち、それがとんでもない勘違いだと気付いた。
クーパーは密かにドゲットの言動に注目し、入局したてのこの男が、何故か彼より先輩の捜査官から信頼されてい
ることや、極端に口数は少ないが、彼の出す指示は何時も的確で、動きやすいことに気付いた。凶悪な逃走犯を冷
徹に追い詰め逮捕にまで持ってゆく手腕は、能無しどころか、稀に見る逸材だ。ふうん、と、クーパーは斜に構えたま
ま、ドゲットの様子を窺っていた。こりゃ、あっという間に出世街道まっしぐらって輩だな。鼻持ちなら無い役人が、又
一人増えるって訳か。まあ、どの道俺には関係ない。
ることや、極端に口数は少ないが、彼の出す指示は何時も的確で、動きやすいことに気付いた。凶悪な逃走犯を冷
徹に追い詰め逮捕にまで持ってゆく手腕は、能無しどころか、稀に見る逸材だ。ふうん、と、クーパーは斜に構えたま
ま、ドゲットの様子を窺っていた。こりゃ、あっという間に出世街道まっしぐらって輩だな。鼻持ちなら無い役人が、又
一人増えるって訳か。まあ、どの道俺には関係ない。
そう判断しドゲットを自分の中から閉め出そうとした矢先、妙なことにクーパーは気付いてしまった。この稀にみる逸
材は、どういうわけか自分の所属する課に埋没して、まるで烏合の衆の如く周りに溶け込んでいる。これは、少し妙
だった。当初クーパーは、ドゲットが考え事があると、屋上に現れたのは、自分の課で未だ居場所が無く、仲間の中
で浮いているからではないかと疑っていた。
材は、どういうわけか自分の所属する課に埋没して、まるで烏合の衆の如く周りに溶け込んでいる。これは、少し妙
だった。当初クーパーは、ドゲットが考え事があると、屋上に現れたのは、自分の課で未だ居場所が無く、仲間の中
で浮いているからではないかと疑っていた。
FBIの中でドゲットは新参者だ。それは彼の年齢からみても分かるし、雰囲気からしても叩き上げの捜査官なのだろ
う。そんな奴が早くも頭角を現し、同じ課の捜査官の出世を脅かす存在となれば、当然敬遠されるはずだ。ところが、
ドゲットを取り巻く風景は、とてもそんな風には見えないのだ。
う。そんな奴が早くも頭角を現し、同じ課の捜査官の出世を脅かす存在となれば、当然敬遠されるはずだ。ところが、
ドゲットを取り巻く風景は、とてもそんな風には見えないのだ。
捜査から離れたドゲットを何時見かけても、大抵パートナーの傍らで和やかに談笑しているか、同じ課の同僚の話
の輪の中にいる。積極的に話をしているようにはとても見えないが、かといって無理してその場にいるようでもない。
それどころか、もう何年も彼らの仲間であるかのような雰囲気だ。ドゲットはいとも簡単に彼らに溶け込み、彼らもまた
何の抵抗も無く、驚くべき速さでドゲットを受け入れたことになる。
の輪の中にいる。積極的に話をしているようにはとても見えないが、かといって無理してその場にいるようでもない。
それどころか、もう何年も彼らの仲間であるかのような雰囲気だ。ドゲットはいとも簡単に彼らに溶け込み、彼らもまた
何の抵抗も無く、驚くべき速さでドゲットを受け入れたことになる。
クーパーは首を捻った。何故だ。何故こうも容易く曲者揃いの連中の中に溶け込めたんだ。やり手の新参者がそん
な風に出来たのを俺は見たことがないぞ。しかもそんな奴が、何故考え事をする為に、わざわざ屋上にやってくるの
だ。俺についての噂が、あの連中から耳に入らないわけがない。実際俺だって相当手酷く追い払っているぞ。おまけ
に他のパイロットに確かめたら、俺のシフトの時しか来ていないだと?何故だ。どういうことだ。
な風に出来たのを俺は見たことがないぞ。しかもそんな奴が、何故考え事をする為に、わざわざ屋上にやってくるの
だ。俺についての噂が、あの連中から耳に入らないわけがない。実際俺だって相当手酷く追い払っているぞ。おまけ
に他のパイロットに確かめたら、俺のシフトの時しか来ていないだと?何故だ。どういうことだ。
そうやって幾らクーパーが頭を巡らせたところで、ヘリの要請が無い限り、局内でちらりと見かける以外ドゲットとの
接触が無い彼に、分かろうはずもない。かといって、階下に親しい人間が一人もいないクーパーが、ドゲットについて
の情報を積極的に得られる術は、PCでドゲットに関する記録を調べる以外ないのだが、そこにある経歴からは、クー
パーが知りたい肝心の情報は何一つ浮かんで来ないのだ。
接触が無い彼に、分かろうはずもない。かといって、階下に親しい人間が一人もいないクーパーが、ドゲットについて
の情報を積極的に得られる術は、PCでドゲットに関する記録を調べる以外ないのだが、そこにある経歴からは、クー
パーが知りたい肝心の情報は何一つ浮かんで来ないのだ。
クーパーは次第に、悪天候の中ヘリを計器飛行しているような気分になってきていた。しかも、ドゲットのことを考え
まいと、頭から払い除けようとすればするほど、余計に様々な疑問が浮かんできて、知らぬ間に又ドゲットのことを考
えているのだ。クーパーは正直うろたえていた。
まいと、頭から払い除けようとすればするほど、余計に様々な疑問が浮かんできて、知らぬ間に又ドゲットのことを考
えているのだ。クーパーは正直うろたえていた。
彼の苦難に満ちた人生経験から得た、唯一の答えは、他人とは係わるな、ということだった。今までのクーパーの
人生で、これ以上無いだろうと思われる最悪の出来事は、全て他人と係わった為に起きていた。破産、事故、死別、
恋人の裏切り、離婚、それら全てを他人と係わったが為に起きた出来事と、クーパーは考えていた。
人生で、これ以上無いだろうと思われる最悪の出来事は、全て他人と係わった為に起きていた。破産、事故、死別、
恋人の裏切り、離婚、それら全てを他人と係わったが為に起きた出来事と、クーパーは考えていた。
勿論、それが全てではないかもしれない。しかし、彼の人生にはあまりに悲惨な出来事が多すぎた。恐らく通常の
人の3倍は、不幸な出来事を背負い込んでいる。となれば、クーパーがそう思い込むことで、辛い体験を乗り切ろうと
するのは、致し方ない現実なのだと言えるし、そうして他者との接触を避けるようになったとしても、彼を責めることは
出来ない。
人の3倍は、不幸な出来事を背負い込んでいる。となれば、クーパーがそう思い込むことで、辛い体験を乗り切ろうと
するのは、致し方ない現実なのだと言えるし、そうして他者との接触を避けるようになったとしても、彼を責めることは
出来ない。
クーパーは、今の職業に安定した時から、もう二度と他人とは係わらない人生を送ろうと心に決めていた。そう決心
したのが40歳になる誕生日だから、かれこれ10年近くになる。そう決心して過ごしてきた日々は、彼が思い描いた
とおり、無味乾燥なまでに平穏で、心を掻き乱されるような思いもなければ、のた打ち回るような苦しみも無かった。
孤独という名のついた彼の城で、クーパーは煩わしい日常から開放され、自己満足という温い空気にどっぷりと浸
り、ぬくぬくとした生活を送っていた。
したのが40歳になる誕生日だから、かれこれ10年近くになる。そう決心して過ごしてきた日々は、彼が思い描いた
とおり、無味乾燥なまでに平穏で、心を掻き乱されるような思いもなければ、のた打ち回るような苦しみも無かった。
孤独という名のついた彼の城で、クーパーは煩わしい日常から開放され、自己満足という温い空気にどっぷりと浸
り、ぬくぬくとした生活を送っていた。
ところがそうして出来上がったクーパーの牙城に、するりと入り込んできた闖入者を、取り込むことも締め出すことも
叶わず、クーパーは焦れていた。何故なら、最後に屋上から追い出してからドゲットが上がってくることは無かったし、
締め出そうと判断した事件を境に、ぱったりとドゲットの姿を見かけなくなったからだ。局内の噂では相当厄介な事件
に、駆り出されているらしかった。
叶わず、クーパーは焦れていた。何故なら、最後に屋上から追い出してからドゲットが上がってくることは無かったし、
締め出そうと判断した事件を境に、ぱったりとドゲットの姿を見かけなくなったからだ。局内の噂では相当厄介な事件
に、駆り出されているらしかった。
クーパーはドゲットが、考え事をしに屋上に現れた3回が、いずれも担当した事件終了直後だと、密かに記録を調べ
突き止めていた。そうなれば今の事件終了後、再びドゲットは屋上にやってくるかもしれない。そこまで、考えてクー
パーは些か、慌てて自分自身に言い聞かせた。これは何もドゲットが来るのを待っているわけじゃない。只、あいつに
確かめたいだけだ。自分のシフトの時ばかり選んで、屋上に来たのは何故か。何故屋上に来るのか。そうとも、それ
さえ聞けばもうあいつに用は無い。追い返せばいいんだ。
突き止めていた。そうなれば今の事件終了後、再びドゲットは屋上にやってくるかもしれない。そこまで、考えてクー
パーは些か、慌てて自分自身に言い聞かせた。これは何もドゲットが来るのを待っているわけじゃない。只、あいつに
確かめたいだけだ。自分のシフトの時ばかり選んで、屋上に来たのは何故か。何故屋上に来るのか。そうとも、それ
さえ聞けばもうあいつに用は無い。追い返せばいいんだ。
そう自分に決まりをつけたというのに、肝心のドゲットが今度は幾ら待っても現れないのだ。クーパーは焦れに焦れ
た。そして、とうとう今までの自分自身に見切りをつけた。クーパーはある決意を固めると、ようやくそれまでの宙ぶら
りんな精神状況から逃れられ、ほっと一息付いて、呟いた。
た。そして、とうとう今までの自分自身に見切りをつけた。クーパーはある決意を固めると、ようやくそれまでの宙ぶら
りんな精神状況から逃れられ、ほっと一息付いて、呟いた。
「くそ。苛付く男だ。今度会ったら・・・。」
しかし、この時もやはり次が浮かばない。何をどう言えばいいのだろう。詰問してものらりくらりと受け答えるし、こちら
が激怒すれば、真面目腐って相槌を打つ。まさに悪天候の計器飛行だ。視界が利かず目的地も定かでは無い。俺
はひょっとして、巨大な雲の中に突っ込もうとしているのかもしれない。クーパーはその時、久方ぶりのスリルに心の
奥底から湧き上がる高揚感を抑えることが出来ずにいた。
が激怒すれば、真面目腐って相槌を打つ。まさに悪天候の計器飛行だ。視界が利かず目的地も定かでは無い。俺
はひょっとして、巨大な雲の中に突っ込もうとしているのかもしれない。クーパーはその時、久方ぶりのスリルに心の
奥底から湧き上がる高揚感を抑えることが出来ずにいた。
それから数週間後の週末。夜半過ぎ、ドゲットは照明を落とした屋上を歩いていた。エレベーターを降りてから、脇
目も降らず電圧室へと向かう。慣れた動作で梯子を上り、上がりきったところで、ふと人の気配を感じ何時もの場所に
目を向ければ、はっとして思わず立ち止まった。何故なら彼が何時も腰掛けている場所に、クーパーがそれと分かる
ほど不機嫌な顔付きで腰掛け、腕組みをしたままこちらを睨んでいる。
目も降らず電圧室へと向かう。慣れた動作で梯子を上り、上がりきったところで、ふと人の気配を感じ何時もの場所に
目を向ければ、はっとして思わず立ち止まった。何故なら彼が何時も腰掛けている場所に、クーパーがそれと分かる
ほど不機嫌な顔付きで腰掛け、腕組みをしたままこちらを睨んでいる。
クーパーは、怪訝そうな顔でドゲットが近づくまで何も言わず、煙草を咥えたまま、微動だにしない。ドゲットはクー
パーの真正面に立ち、両手をズボンのポケットに突っ込んで、気まずそうな顔で上目にクーパーの顔を眺め、口を開
きかけた。が、それを遮るようなクーパーの乱暴な声がした。
パーの真正面に立ち、両手をズボンのポケットに突っ込んで、気まずそうな顔で上目にクーパーの顔を眺め、口を開
きかけた。が、それを遮るようなクーパーの乱暴な声がした。
「遅いぞ。」
え?という顔になったドゲットなど、クーパーは構っちゃいない。
「立ってないで座れ。鬱陶しい。」
ドゲットは益々眉間の皺を深くしたが、ここは逆らわない方が得策と判断したのか、大人しく彼の横に腰掛けた。相変
わらず不機嫌な声でクーパーは畳みかけた。
わらず不機嫌な声でクーパーは畳みかけた。
「担当してた事件は3日前に終わったんだろ?」
「・・・ええ。」
「終わったのに、何やってたんだ。」
「ああ、今回犠牲者が多く、その事後処理に手間取ったんです。」
「そいつは、お前の仕事なのか?」
ドゲットは俯いたまま、曖昧に頷いた。ドゲット達が追っていたのは、通称ハイウェイキラーと呼ばれ、車で移動しなが
らハイウェイ沿いに殺しを重ねる凶悪犯だった。犯人は行く先々で死体の山を築き、ほぼ全米を荒らしまわった。ドゲ
ットが捜査に加わったのは、最初に事件が起きてから、これが同一犯の連続殺人事件で、今も尚犯行を重ねている
と発覚した一ヶ月前からなのだが、犯人を特定し足取りを追う為に費やされた時間と労力は並大抵では無かった。
らハイウェイ沿いに殺しを重ねる凶悪犯だった。犯人は行く先々で死体の山を築き、ほぼ全米を荒らしまわった。ドゲ
ットが捜査に加わったのは、最初に事件が起きてから、これが同一犯の連続殺人事件で、今も尚犯行を重ねている
と発覚した一ヶ月前からなのだが、犯人を特定し足取りを追う為に費やされた時間と労力は並大抵では無かった。
苦心の末犯人の足取りを掴み、メキシコとの国境近くのガソリンスタンドに、国外逃亡を計った犯人を追い詰め、ス
タンドに立てこもった犯人と派手な銃撃戦を展開し、犯人射殺という形で、ようやく事件の終結を見たのだった。しか
し、銃撃戦の際、FBIや地元警察側に多大な犠牲者を出した為、誰かが責任を問われることのなるだろうというのが、
FBI内でのもっぱらの噂だった。
タンドに立てこもった犯人と派手な銃撃戦を展開し、犯人射殺という形で、ようやく事件の終結を見たのだった。しか
し、銃撃戦の際、FBIや地元警察側に多大な犠牲者を出した為、誰かが責任を問われることのなるだろうというのが、
FBI内でのもっぱらの噂だった。
幾ら階下と接触していないクーパーでも、新聞の一面を飾る大事件を知らないはずも無く、それにドゲットが駆り出
されていたとしても、最早ドゲットの実力を知った今では、不思議でも何でもない。クーパーは顔を背けたまま、口を噤
んでしまったドゲットの横顔を、ちらりと見てから更に尋ねた。
されていたとしても、最早ドゲットの実力を知った今では、不思議でも何でもない。クーパーは顔を背けたまま、口を噤
んでしまったドゲットの横顔を、ちらりと見てから更に尋ねた。
「撃たれたのは誰だ?」
「内の課のシングルトン。」
「黒い方か、白い方か?」
ドゲットは顔を顰めると、ちょっと険しい目をしてクーパーを見詰め、一呼吸置いて答えた。
「サム・シングルトン。」
「ああ、あいつか。黒い方だな。」
ドゲットはむすっとして下を向いた。明らかにクーパーの無神経な人種差別的発言を不快に感じてるようだった。しか
し差別的な発言を、人にどう取られようが屁でもないクーパーは、ドゲットの様子など、構うことなく先を続ける。
し差別的な発言を、人にどう取られようが屁でもないクーパーは、ドゲットの様子など、構うことなく先を続ける。
「死んだのか?」
「いいえ。」
「そりゃ、良かったな。警察の方は、ええっと、何人だ・・そう、確か2人死んでるんだろ?ラッキーだったな。」
それを聞いたドゲットは、歪んだ笑みを浮かべ横を向く。それを目ざとく見咎め、クーパーは更に尋ねた。
「命が助かったんだ。良かったじゃねえか。」
「まあ、そうでしょうね。」
「何だ。違うとでも言いたそうだな。勿体ぶらずに言えよ。」
ドゲットは、少し躊躇っていたが、やがて小さく息をつくと、こう言った。
「確かに命は助かりましたが、シングルトンの現場復帰は難しいでしょう。犯人の撃った弾が背骨を砕いたんです。」
「砕いた?ベストは着てたんだろ?そんな大層な弾だったのか?」
「強装弾。」
「ホットロードか。そんなもの死人が出るほど撃ちまくったら、直ぐに銃はガラクタだぞ。」
「犯人は銃が破損しても直ぐに補充出来るよう、ホットロード用の44マグナムを何丁も所持していたんです。」
「じゃあ、流れ弾ってわけか。車のトランク一杯銃器が入ってたんだっけな。だがホットロードで撃たれて命が助かっん
だ。シングルトンは相当運がいいと言えるんじゃねえのか?」
だ。シングルトンは相当運がいいと言えるんじゃねえのか?」
「確かに手術で命は取り留めましたが、未だに意識不明の重体ですし、意識が戻っても恐らく半身不随、下手をすれ
ば首から下は一生動かないというのが、医者の診断です。死んだ方がましだとは決して言いませんが、この先の彼
と彼の家族の苦労を思うと、手放しでは喜べませんね。」
ば首から下は一生動かないというのが、医者の診断です。死んだ方がましだとは決して言いませんが、この先の彼
と彼の家族の苦労を思うと、手放しでは喜べませんね。」
淡々とした表情で語るドゲットの顔を、クーパーは、へえっ、という顔で眺めていた。よほどその様子が妙だったのだ
ろう。それに気付いたドゲットが、不思議そうに尋ねた。
ろう。それに気付いたドゲットが、不思議そうに尋ねた。
「何です?」
「お前、今、随分長く喋ったな。」
それを聞いたドゲットは、拍子抜けしたような顔つきになり、何ですかそりゃ、などと呟きそっぽを向く。喋りすぎたなと
いう顔をして、気まずそうに顔を背けるドゲットを、クーパーはにやにやしながら横目で見ていた。こりゃ、面白い。形
勢逆転だぞ。何時もの癪に障る落ち着き払った態度を、僅かでも崩せたのだ。クーパーは、心の中でガッツポーズを
していた。だがクーパーは、ドゲットの切り替えしの鋭さを、この時はまだ知らなかったのだ。最後にほくそえむのは
誰か、この時は予想だにしていなかった。
いう顔をして、気まずそうに顔を背けるドゲットを、クーパーはにやにやしながら横目で見ていた。こりゃ、面白い。形
勢逆転だぞ。何時もの癪に障る落ち着き払った態度を、僅かでも崩せたのだ。クーパーは、心の中でガッツポーズを
していた。だがクーパーは、ドゲットの切り替えしの鋭さを、この時はまだ知らなかったのだ。最後にほくそえむのは
誰か、この時は予想だにしていなかった。
「あなたは、ここで何をしていたんです?」
「俺か?俺はその・・・・」
ドゲットを待っていたとは、とてもクーパーの口からは言えない。口籠って答えあぐねていると、更にドゲットは尋ねてく
る。
る。
「事件の話を?」
「あ、いや、その・・うむ。」
「知り合いが絡んでいたとか?」
「いや、違う。」
ドゲットは眉間に皺を寄せちょっと考えてから、何時もの真面目腐った口調で確認してきた。
「まさか僕を待っていたわけじゃあ、無いですよね。」
「ば、馬鹿な!」
図星を指され思わず強い口調で否定したものの、その不自然な態度にドゲットは訝しげに顔を顰め、クーパー自身も
うろたえ気味に目を泳がせる。自分の言葉で口を噤んでしまったドゲットとの間が持たず、クーパーは苛々と立ち上
がった。
うろたえ気味に目を泳がせる。自分の言葉で口を噤んでしまったドゲットとの間が持たず、クーパーは苛々と立ち上
がった。
「とにかく・・」
とにかく?言ってから、クーパーしまったと舌打ちした。その先に続く言葉が無い。この場合、次の台詞に繋げる接続
詞は別のものだ。しかしその接続詞は、ここにいた理由を述べる台詞に繋げてしまう。そんなこと言えるか。クーパー
は、ドゲットの真正面に横向きに立ち、前を向いたまま、構わずその先を続けることにした。
詞は別のものだ。しかしその接続詞は、ここにいた理由を述べる台詞に繋げてしまう。そんなこと言えるか。クーパー
は、ドゲットの真正面に横向きに立ち、前を向いたまま、構わずその先を続けることにした。
「とにかくだ。これからここを使うんだったら俺に一言断ってから、ここに上がれ。突然出動がかかって緊急離陸させる
時、うろちょろされると危ねえんだよ。」
時、うろちょろされると危ねえんだよ。」
「追い返さないんですか?」
「あぁ?追い返して欲しいのか?」
「・・・いえ、只その・・」
「何だ?文句でもあるって言うのか?」
「いえ、ありません。」
「じゃあ黙って俺の言うことを聞け。それ以上、うだうだぬかしやがると、出入り禁止にするぞ。」
「そいつは困る。」
出入り禁止と聞いて即座にそう答えたドゲットに向き直り、クーパーはにやりと笑って言った。
「俺の言うことを聞くんだな。」
「勿論。」
従順な態度で頷くドゲットの様子に気を良くしたクーパーは、ツナギのポケットから小さく折りたたんだ紙切れを取り出
すと、ドゲットに放って寄こした。するとドゲットは、苦も無く片手で受け止め、手の中の紙切れを見詰め、何です?と
聞いてきた。
すと、ドゲットに放って寄こした。するとドゲットは、苦も無く片手で受け止め、手の中の紙切れを見詰め、何です?と
聞いてきた。
「俺のシフト表だ。一ヶ月そのローテーションで回る。お前にやるから、好きに使え。」
ドゲットは黙って手元の紙を見詰めたまま動かない。
「何か文句でもあるのか?」
「いいえ、只、何故かな、と思って・・。」
「何故だろうとお前にゃ関係ない。いらないなら、返せ。」
「いえ、貰っておきます。」
そしてドゲットは、クーパーを見上げ、ありがとうと言って、にっこりと笑った。その邪気のない笑顔は、クーパーを良い
気分にさせたのは言うまでも無く、人にそんな風に感謝の言葉を述べられることに慣れていないクーパーの心を、自
尊心で満たした。久方ぶりの心境にくすぐったさを覚え、照れくささにわざと乱暴な口調で、失くすなよ、などと言え
ば、大事そうにポケットにしまい込むドゲットの姿があった。クーパーは満足げに頷くと、威張り腐った態度で命令す
る。
気分にさせたのは言うまでも無く、人にそんな風に感謝の言葉を述べられることに慣れていないクーパーの心を、自
尊心で満たした。久方ぶりの心境にくすぐったさを覚え、照れくささにわざと乱暴な口調で、失くすなよ、などと言え
ば、大事そうにポケットにしまい込むドゲットの姿があった。クーパーは満足げに頷くと、威張り腐った態度で命令す
る。
「それと、もう一つ。お前のその喋り方だ。そいつを何とかしろ。」
「意味が分かりませんが。」
「ほら、それだ。その癇に障る敬語を止めろ。糞丁寧な言葉は、虫唾が走るんだよ。言いたいことは、何でも好きに言
って構わんが、敬語は使うな。」
って構わんが、敬語は使うな。」
「・・・何でも?」
「そうだ。俺以外の奴にこそこそされるのも気に食わんし、俺に気を使った話をされるのはもっと腹が立つ。いいか、こ
れからは俺のことはクーパーと呼べ。それ以外の呼び方じゃ返事しねえぞ。分かったか。」
れからは俺のことはクーパーと呼べ。それ以外の呼び方じゃ返事しねえぞ。分かったか。」
「了解。」
ドゲットは真顔で頷き答える。クーパーは機嫌よくにんまり笑うと、踵を返し電圧室を降りようと梯子に戻りかけたが、
早速後ろから、クーパーと、呼ばれ振り返った。
早速後ろから、クーパーと、呼ばれ振り返った。
「何だ。話は終わってるぞ。まだ何かあるのか。」
「ある。大有りだ。」
「何だと?」
心当たりの無いクーパーが顔を顰めると、平然と見返しドゲットは答えた。
「吸殻を片付けろ。」
ドゲットの視線の先には、クーパーが吸い散らかした吸殻が、何本も落ちている。たった今、何でも言ってよし、といっ
た手前、ぐうの音も出ないクーパーは、むすっとしてドゲットの元へ戻ると、足元に屈んで吸殻を拾い始めた。
た手前、ぐうの音も出ないクーパーは、むすっとしてドゲットの元へ戻ると、足元に屈んで吸殻を拾い始めた。
その時クーパーは、俯くドゲットの口元が僅かに綻んでいるのを認め、おやっと、眉を顰めた。もしかしたらこいつ、こ
の俺を、おひゃらかしてたんじゃあるまいな。そう言えば、何時の間にか、こいつのペースだ。しかし直ぐに、頭を振る
と、その考えを打ち消した。まさかな。糞真面目なこの男に、そんな芸当が出来るわけが無い。しかも、拾い終わって
見上げたドゲットからは、そんな表情は少しも窺えないのだ。クーパーは拾い集めた吸殻を片手で握り立ち上がると、
横柄な口調で聞いた。
の俺を、おひゃらかしてたんじゃあるまいな。そう言えば、何時の間にか、こいつのペースだ。しかし直ぐに、頭を振る
と、その考えを打ち消した。まさかな。糞真面目なこの男に、そんな芸当が出来るわけが無い。しかも、拾い終わって
見上げたドゲットからは、そんな表情は少しも窺えないのだ。クーパーは拾い集めた吸殻を片手で握り立ち上がると、
横柄な口調で聞いた。
「これでいいか。」
「上出来だ。」
「もう、戻ってもいいんだな。」
「勿論。」
クーパーは直ぐにでも、立ち去るはずだった。しかし、何故か尚もそこに留まっている。ドゲットはそんなクーパーを、
何だ?という顔で見上げた。すると、クーパーは所在無げに暫し視線を泳がせていたが、急に正面切って尋ねてき
た。
何だ?という顔で見上げた。すると、クーパーは所在無げに暫し視線を泳がせていたが、急に正面切って尋ねてき
た。
「どうしてだ?」
「何が?」
「だから、考え事をするのに、何故ここなんだ。」
するとドゲットは、ああ、と言って少し俯くと、静かな口調で答えた。
「ここは、雑音が無いからだ。」
「雑音?・・ふん、雑音ね。じゃあ、俺のシフトの時ばかりなのは、何故だ。」
「そりゃ、一番面倒そうじゃ無かったからさ。」
「俺がか?この俺に三回も追い返されてるのに?」
「だがそれを知る奴はいない。何故だ?」
「そりゃ、誰にも話してないからに決まってる・・・。」
そこでクーパーは、ははあ、と頷いて呟いた。
「そういうことか。」
その声が聞こえたのか、ふふと無言で笑うドゲットの顔を眺め、クーパーは何となく分かったような気がして、ふうんと
ドゲットの顔を覗きこんだ。するとそれに気付いたドゲットが、極まり悪そうに2、3回咳払いして、ちょっといい訳がま
しく答えた。
ドゲットの顔を覗きこんだ。するとそれに気付いたドゲットが、極まり悪そうに2、3回咳払いして、ちょっといい訳がま
しく答えた。
「邪魔が入るのが嫌いな性質なんだ。」
「成る程。」
クーパーは、したり顔で頷くと、じゃあ、俺は戻る、そう言って梯子を降りかけ、思い出したように、もう一度念押しし
た。
た。
「いいか。来た時と、帰る時は、俺に一言言うのを忘れんな。」
ドゲットが黙って頷くのを確認して、クーパーは梯子を降りた。詰め所に戻りながら、どうしてこういう展開になったんだ
ろうと、クーパーは首を捻った。理由を聞き質したら、追い返して立ち入り禁止にするはずじゃ、無かったのか?しか
し、そう出来なかった理由を、クーパーは直ぐに思い当たった。あんな顔をしてる奴を、追い返せるか。畜生。クーパー
は腹立たしげに舌打ちして、手に持っていた吸殻を地面に叩き付けた。
ろうと、クーパーは首を捻った。理由を聞き質したら、追い返して立ち入り禁止にするはずじゃ、無かったのか?しか
し、そう出来なかった理由を、クーパーは直ぐに思い当たった。あんな顔をしてる奴を、追い返せるか。畜生。クーパー
は腹立たしげに舌打ちして、手に持っていた吸殻を地面に叩き付けた。
益々酷くなる雨を、ドゲットは飽きることなく見詰め続けている。その横顔を眺めながら、あれから5年か、とクーパー
は時の経つことの速さに暫ししみじみとした感慨に耽った。あの時、俺はこの男と決着を付けようと待ち構えていた。
だが、出来なかった。そこまで考えたところで、視線を感じたドゲットが、前を向いたままクーパーに言った。
は時の経つことの速さに暫ししみじみとした感慨に耽った。あの時、俺はこの男と決着を付けようと待ち構えていた。
だが、出来なかった。そこまで考えたところで、視線を感じたドゲットが、前を向いたままクーパーに言った。
「何だ。」
「いや。・・よく降るな。」
再びドゲットは黙ってしまう。既に日はとっぷりと暮れ闇が視界を遮り、激しい雨音だけが2人を包む。ドゲットの視線
の先には、窓に打ちつける幾筋もの雨の雫があるだけなのに、何を思ってか先ほどからずっと同じところを見続けて
いる。
の先には、窓に打ちつける幾筋もの雨の雫があるだけなのに、何を思ってか先ほどからずっと同じところを見続けて
いる。
クーパーには、もうとっくにこういうときのドゲットが、何を見ているのか察しが付いている。そして、5年前どうして自
分がドゲットを追い返せなかったかも、今となっては自分なりに納得してはいた。あの日クーパーは、電圧室の上で
今か今かと、てぐすね引いて、ドゲットを待っていた。用が済んだら追い出そうと、心に決めていた。だが、梯子を上が
ってきたドゲットの顔を一目見た途端、言葉を失った。
分がドゲットを追い返せなかったかも、今となっては自分なりに納得してはいた。あの日クーパーは、電圧室の上で
今か今かと、てぐすね引いて、ドゲットを待っていた。用が済んだら追い出そうと、心に決めていた。だが、梯子を上が
ってきたドゲットの顔を一目見た途端、言葉を失った。
何だ、こいつ。この惨めったらしい負け犬の顔はなんだ。それに、この顔は何処かで・・・。クーパーは正直驚いてい
た。それはあまりにドゲットに似つかわしくない。ドゲットはそこにクーパーがいるなど思いもしなかったのだろう。だ
が、だからこそそれは決して人に見せることに無い、彼の素顔だった。クーパーは自分がそこにいると気付いて、かき
消すように無くなってしまったドゲットのその表情が気になって仕方なかった。
た。それはあまりにドゲットに似つかわしくない。ドゲットはそこにクーパーがいるなど思いもしなかったのだろう。だ
が、だからこそそれは決して人に見せることに無い、彼の素顔だった。クーパーは自分がそこにいると気付いて、かき
消すように無くなってしまったドゲットのその表情が気になって仕方なかった。
クーパーはその後ドゲットと言葉を交わすうち、そうだ見覚えがあると思ったあれは、以前の俺の顔なのだと思い当
たった。己の無力さに打ちのめされ、鬱積した敗北感に見舞われた人間がああいう顔になる。だがドゲットが、そんな
顔付きになる理由が見当たらない。クーパーから見ればドゲットは、前途洋洋、出世街道まっしぐら、彼の先には明る
い未来しかありえない栄誉と成功を収める勝者の人生だ。そんな男が、何故あんな顔をしているのか見当も付かな
い。結局、幾つかの疑問は解消されたが、新たに疑問が芽生えただけだ。
たった。己の無力さに打ちのめされ、鬱積した敗北感に見舞われた人間がああいう顔になる。だがドゲットが、そんな
顔付きになる理由が見当たらない。クーパーから見ればドゲットは、前途洋洋、出世街道まっしぐら、彼の先には明る
い未来しかありえない栄誉と成功を収める勝者の人生だ。そんな男が、何故あんな顔をしているのか見当も付かな
い。結局、幾つかの疑問は解消されたが、新たに疑問が芽生えただけだ。
しかし、クーパーにはもうドゲットを締め出そうという気が無くなっていた。それは、あんな顔になってしまった時の、
精神状態がどれほどのものか、身を持って体験済みだからだ。クーパーはあの時詰め所に戻り、ドゲットのいる電圧
室の方を向いて、力無く呟いた。
精神状態がどれほどのものか、身を持って体験済みだからだ。クーパーはあの時詰め所に戻り、ドゲットのいる電圧
室の方を向いて、力無く呟いた。
「くそ。苛付く男だ。・・・だがまあ、苛付く男だが、一人ぐらい邪魔にはならんだろう。」
5年前ドゲットに示した態度が、同情とは言い難いが、何かこの男に自分と同じ匂いを嗅ぎ取っていたのも事実だ。
その証拠に、ドゲットほどクーパーを苛付かせない男は他にいなかった。大抵ドゲットは、何か大きな事件が終わる
と、ふらっとやって来て、詰め所かへりの近くにいるクーパーに、やあ、と声をかける。そして、そのまま例の場所に上
がってしまう。それは、ほんの数十分のこともあれば、何時間にも及ぶ時もある。やがて気が済んだのか、降りてき
たドゲットは再びクーパーに、じゃあな、などと言って去ってゆく。それだけだ。
その証拠に、ドゲットほどクーパーを苛付かせない男は他にいなかった。大抵ドゲットは、何か大きな事件が終わる
と、ふらっとやって来て、詰め所かへりの近くにいるクーパーに、やあ、と声をかける。そして、そのまま例の場所に上
がってしまう。それは、ほんの数十分のこともあれば、何時間にも及ぶ時もある。やがて気が済んだのか、降りてき
たドゲットは再びクーパーに、じゃあな、などと言って去ってゆく。それだけだ。
この1、2年で、ようやく詰め所でコーヒーを飲むまでになったが、それもやはりこういう突発的な悪天候に見舞われ
たときのみで、だからと言って、気安く何でも話す仲になったという訳でもなく、大抵はこうして2,3言葉を交わし、お
互いに気が向けば与太話をして苦笑しあう。一定の距離を置いた、気楽な関係だった。しかし、クーパーはそれでい
いと思っていた。それは何年もドゲットと付き合ううち、何故ドゲットがここに来るのか朧げにだが分かり始めていたか
らだった。
たときのみで、だからと言って、気安く何でも話す仲になったという訳でもなく、大抵はこうして2,3言葉を交わし、お
互いに気が向けば与太話をして苦笑しあう。一定の距離を置いた、気楽な関係だった。しかし、クーパーはそれでい
いと思っていた。それは何年もドゲットと付き合ううち、何故ドゲットがここに来るのか朧げにだが分かり始めていたか
らだった。
たった一瞬見せたあの表情を、再びクーパーの前でドゲットは見せることは無かったが、それでもクーパーにはドゲ
ットの抱えるものが何なのか、おおよその見当がついた。素晴らしい事件解決率を誇る有能なこの男は仕事では多
大な成功を収め、着々と出世コースを歩んでいる。彼の周りにいる人間は、そんなドゲットに賞賛を惜しまないし、彼
と一緒に働くことを望むものが大勢いる。しかし、ドゲットの望むものは、恐らく他にあるのだ。
ットの抱えるものが何なのか、おおよその見当がついた。素晴らしい事件解決率を誇る有能なこの男は仕事では多
大な成功を収め、着々と出世コースを歩んでいる。彼の周りにいる人間は、そんなドゲットに賞賛を惜しまないし、彼
と一緒に働くことを望むものが大勢いる。しかし、ドゲットの望むものは、恐らく他にあるのだ。
クーパーは確信していた。ドゲットは、何かを捨てにここへ来る。それが何かは分からない。がしかし、何かに折り
合いをつけ、自分自身に始末をつける為に、彼は独りになりたいのだ。そうしたいドゲットの気持ちは、なんとなく分か
るような気がする。酷い精神状態の時に、それを分かる相手に言えば解消されるが、分からない人間に幾ら話しても
虚しいだけで、却って疲労が増す。
合いをつけ、自分自身に始末をつける為に、彼は独りになりたいのだ。そうしたいドゲットの気持ちは、なんとなく分か
るような気がする。酷い精神状態の時に、それを分かる相手に言えば解消されるが、分からない人間に幾ら話しても
虚しいだけで、却って疲労が増す。
一見して誰にでも受け入れられるドゲットが、そういったことを誰にも話す相手がいないなど、始めはちょっと信じ難
かった。しかし、誰の側にでも平然と立てるドゲットが、実は誰も自分の側に立たせないことに、クーパーは気付いて
しまった。見た目のドゲットをそのまま受け取る人間には、ドゲットは非常に分かり易い人間だ。しかしもっと深く彼を
知ろうとすれば、まるで霧の中をあてもなく歩き回るように、ぼんやり見える影の周辺を頼りなく彷徨うことになる。
かった。しかし、誰の側にでも平然と立てるドゲットが、実は誰も自分の側に立たせないことに、クーパーは気付いて
しまった。見た目のドゲットをそのまま受け取る人間には、ドゲットは非常に分かり易い人間だ。しかしもっと深く彼を
知ろうとすれば、まるで霧の中をあてもなく歩き回るように、ぼんやり見える影の周辺を頼りなく彷徨うことになる。
そうして、詰まるところクーパーさえ、未だにドゲットの実像が掴めずにいるのだ。あの時俺は、雲の中に突っ込もう
としていると思ったが、まさにその通りだった。ドゲットの本当の姿は厚い雲に覆われた山中にあり、今目の当たりに
しているこの姿は、男の影なのだ。だが、影にしてはあまりにはっきりしすぎている為、皆それに気付かず騙されてし
まう。それをドゲットが望んでそうしているのか、そうではないのか、クーパーには計りかねた。しかし、これだけは断
言できた。ドゲットはクーパーが創り上げた城より、もっと深く、うそ寒いぐらい人のいない城の、住人なのだ。
としていると思ったが、まさにその通りだった。ドゲットの本当の姿は厚い雲に覆われた山中にあり、今目の当たりに
しているこの姿は、男の影なのだ。だが、影にしてはあまりにはっきりしすぎている為、皆それに気付かず騙されてし
まう。それをドゲットが望んでそうしているのか、そうではないのか、クーパーには計りかねた。しかし、これだけは断
言できた。ドゲットはクーパーが創り上げた城より、もっと深く、うそ寒いぐらい人のいない城の、住人なのだ。
クーパーは我知らず溜息を付いた。只単に人が周りにいなくて味わう孤独感と、人が周りに大勢いる中で味わう孤
独感では、後者の方がとんでもなく辛い。自ら孤独の中に身を置くのと、どうしようもない状況で孤独の中に留まるの
とでは、後者の方が信じられないほどきつい。自分はそれが分かっていても、この孤高の男には手が届かない。出
来るのは、こうしてこの場所を提供するだけだ。
独感では、後者の方がとんでもなく辛い。自ら孤独の中に身を置くのと、どうしようもない状況で孤独の中に留まるの
とでは、後者の方が信じられないほどきつい。自分はそれが分かっていても、この孤高の男には手が届かない。出
来るのは、こうしてこの場所を提供するだけだ。
多分この男は、並大抵の精神力では無いのだろう。こうして、何時もこうやって自分独りで解決してきたのだ。しか
し、それは又恐ろしく精神を疲弊させる。磨り減った精神をこの男はこの先、どうやって保つというのだ。クーパーは次
第に気分が滅入り始め、思わず心の中で呟いた。止めときゃ良かった。他人を心配して落ち込むなんて、他人と係わ
るなんて、間違った判断だった。そこで気分を変えようと、コーヒーのお代わりをしに立ち上がったクーパーの眼に、ド
ゲットの様子が何時もと違っているように見え、おやっと眼を見張った。
し、それは又恐ろしく精神を疲弊させる。磨り減った精神をこの男はこの先、どうやって保つというのだ。クーパーは次
第に気分が滅入り始め、思わず心の中で呟いた。止めときゃ良かった。他人を心配して落ち込むなんて、他人と係わ
るなんて、間違った判断だった。そこで気分を変えようと、コーヒーのお代わりをしに立ち上がったクーパーの眼に、ド
ゲットの様子が何時もと違っているように見え、おやっと眼を見張った。
首を捻りながら、ドゲットに眼を向けたままコーヒーを注ぐ。おかしい。やっぱり何時もと違うぞ。何処がどういうわけ
ではないが、雰囲気が微妙に軽い。クーパーはむくむくと擡げてきた疑問を、抑えられず、ちょっと鎌をかけてみようと
思い立った。コーヒーを手に再び椅子に腰掛けると、ドゲットの様子をちらちらと窺いながら、何気なくこう聞いた。
ではないが、雰囲気が微妙に軽い。クーパーはむくむくと擡げてきた疑問を、抑えられず、ちょっと鎌をかけてみようと
思い立った。コーヒーを手に再び椅子に腰掛けると、ドゲットの様子をちらちらと窺いながら、何気なくこう聞いた。
「アリゾナの事件はかたがついたのか。」
「ああ。」
「終りなのか?見つかってないのにか?」
「そうだ。」
「誰の判断だ?カーシュか?」
「そうだ。」
相変わらず素っ気無いドゲットの返事だが、それは今に始まった話ではない。ふうん、とクーパーは頷きちょっと考え
てから先を続けた。
てから先を続けた。
「大方、アリゾナくんだりまで大勢出動して空振りだったから、世間体がとか、笑いものだとか、そんな下らんことで捜
索班を解散したんだろう。」
索班を解散したんだろう。」
ドゲットは黙って無表情に外を見ている。クーパーは、構うことなく尋ねた。
「待てよ。じゃあ、この責任は一体誰に取らせるんだ。捜索は失敗だったんだろう?あのカーシュが音沙汰なしなん
て、考えられん。誰かに責任を押し付けたに決まってる。その不幸な奴は誰だ?」
て、考えられん。誰かに責任を押し付けたに決まってる。その不幸な奴は誰だ?」
「俺だ。」
「は?」
如何にも平然と即答したドゲットに思わず気の抜けた返事をしたクーパーは、眼を白黒させた。クーパーはマグカップ
をデスクに置くと、ドゲットに向き直った。
をデスクに置くと、ドゲットに向き直った。
「まあ、確かにお前の仕切りだったが、お前を指名したのはカーシュだし、捜索にはスキナーも加わっていたじゃねえ
か。お前の他にも責任取らされた奴がいるんだろう?」
か。お前の他にも責任取らされた奴がいるんだろう?」
「いない。」
「いない?そんな馬鹿な。」
そう言って絶句したクーパーをちらりと見てから、ドゲットは再び前を向いた。クーパーは事態がまだ良く飲み込めず、
更に尋ねた。
更に尋ねた。
「じゃ、お前が全責任を負ったのか?」
「ああ。」
「で、一体どう責任を取らされたんだ?」
「配属替えだ。」
「左遷か?」
「さあな。」
「何だ。はっきりしねえな。何処かド田舎に飛ばされるのか?」
「いや、本部内というのは変わらん。」
「本部内?証拠管理課か?まさか経理じゃねえだろうな。」
経理とは犬猿の仲のクーパーを良く知るドゲットはにやりとして、下を向くと首を振った。焦れたクーパーは険しい眼を
して聞き質した。
して聞き質した。
「じゃあ、一体何処なんだ?勿体ぶらずに早く言えよ。」
「X−ファイル課だ。」
「何!?そりゃお前、嘘だろ?」
「本当だ。昨日正式な通達があった。」
X-ファイル?クーパーは口の中でもう一回繰り返すと、うーんと言って腕組みをした。
「X-ファイルっていやあ、例の捜査官が失踪した課だろ?確かに欠員が出たから補充はしなけりゃなるまいが、そこ
に捜索班を仕切ってたお前を配属するってえのは、どうかと思うぜ。」
に捜索班を仕切ってたお前を配属するってえのは、どうかと思うぜ。」
「どうかって?」
「そりゃお前、やり難いに決まってるじゃねえか。捜索は失敗だったんだ。課に残ってる奴がお前のことを歓迎してく
れるとでも、思ってんのか?」
れるとでも、思ってんのか?」
「いや。」
「だろう?で、今度の上司は誰だ?」
「上司はいない。」
「ああ、そういや、あそこは特殊だったな。じゃあ、残ってんのは何人だ?」
「1人。」
「1人?じゃあ、X−ファイルってお前を含めて2人なのか?」
「失踪しているのを含めれば、3人だが、まあそうなるな。」
そこでクーパーは何かに思い当たり、片手を上げた。
「ちょ、ちょっと待て。ちょっと待てよ。残ってる1人ってあの、ちっこくて威勢のいい赤毛のねえちゃんか。」
ドゲットはじろりとクーパーに一瞥をくれたが、何も言わず黙って頷いた。うへっ、とクーパーは声を上げた。
「そりゃあ、お前、随分と厄介なところに配属されちまったもんだな。課も課なら、同僚も同僚だぞ。暫くはあのねえち
ゃんの下で、動かにゃならんとは、難儀な話だ。」
ゃんの下で、動かにゃならんとは、難儀な話だ。」
「そうか。」
「そうに決まってるだろう?只でさえ女の下ってのは、働きにくいのに、あのねえちゃんじゃもっと大変だ。」
「スカリー。」
「何?」
「彼女の名前は、ダナ・スカリーだ。」
そう訂正したドゲットの口調は、クーパーでさえぎくりとするほど厳しかった。しかし自分が認めた人間以外を全て差
別してかかるクーパーに、人種差別や男女差別の是非を説いたところで無駄な努力だ。だが、それでも同僚をねえち
ゃん呼ばわりされるのは、気に食わないのだろう。だからといってそんなことで怯むようなクーパーではない。全く頓
着せず話を続ける。
別してかかるクーパーに、人種差別や男女差別の是非を説いたところで無駄な努力だ。だが、それでも同僚をねえち
ゃん呼ばわりされるのは、気に食わないのだろう。だからといってそんなことで怯むようなクーパーではない。全く頓
着せず話を続ける。
「大体お前、あの、ねえ・・じゃない、ええっとスカリーだっけか。スカリーに捜索中散々噛み付かれてたじゃねえか。」
「パートナーが失踪したんだ。当然だろう。」
「お前に水ぶっかけたって聞いたぞ。」
ドゲットは呆れたようにクーパーを見て、首を振った。
「そんなことまで伝わってるのか。信じられんな。」
「信じられんのはお前の方だ。スカリーはお前を相当嫌ってるぞ。そんな女の下で働くことを何とも思わないのか?」
「別に。」
落着き払ったドゲットの態度が、クーパーには全く理解できなかった。そこで今度は質問を変えてみた。
「ひょっとしてお前、女と仕事したことがねえのか?」
「いいや。」
「じゃ、どれだけやり難いかも知ってるんだな。」
「そうだな。」
「何だ?そりゃ。女と仕事をしても平気なのか。」
「男とか女とか大した問題じゃないからな。」
「大した問題じゃない?そりゃ大間違いだぞ。俺の経験から言うと、女の同僚ってのは細けえし、変なことにこだわる
し、ちょっとしたことでへそを曲げるし、いざとなれば女だからと甘えるし。まあ甘えてくりゃまだ可愛いが、こういう男
ばっかりの職場にいる女は、理屈っぽいし、扱い方を少しでも間違えると、むきになって、セクハラだ、差別だって大
騒ぎだ。ありゃ実際、敵わねえぞ。」
し、ちょっとしたことでへそを曲げるし、いざとなれば女だからと甘えるし。まあ甘えてくりゃまだ可愛いが、こういう男
ばっかりの職場にいる女は、理屈っぽいし、扱い方を少しでも間違えると、むきになって、セクハラだ、差別だって大
騒ぎだ。ありゃ実際、敵わねえぞ。」
「そうか。」
「何だ。違うとでも言うのか?」
ドゲットは少し考えてから答えた。
「本当に有能な人間と仕事をするなら、やり易さの面では女の方が勝っていると俺は思う。」
そう言ってにやりとしてクーパーを見ると、こう付け加えた。
「これは俺の経験だがね。」
「そいつがあのスカリーだって言うのか?」
ドゲットはさっとクーパーの顔を見たが何も答えず、黙ってデスクに両肘を突くと窓の外を覗き込んだ。クーパーは今
のドゲットの発言を反復しながら、少し驚いていた。何故ならどんな形にせよ、ドゲットが特定の女について語るのを
初めて聞いたからだ。
のドゲットの発言を反復しながら、少し驚いていた。何故ならどんな形にせよ、ドゲットが特定の女について語るのを
初めて聞いたからだ。
知り合ってからの5年の間、ドゲットの周りに女の姿がちらつくことは無かったし、浮いた噂一つ無く、呆れるほど殺
風景な生活ぶりは、幾らクーパーでも簡単に推測出来た。しかもクーパーのする卑猥な与太話を笑って聞いてはいる
が、自らその話に便乗することは無いし、女性職員に対する下世話なジョークも苦笑するだけで黙って聞き流すのみ
だ。独身でこれほどの男が、何年も女っ気無しって言うのがどうにも解せず、ある日与太話のついでに、まさかホモじ
ゃあるまいなと問えば、恐ろしい顔で睨まれ、下らんことを言う暇があるなら仕事をしろと凄まれてしまい、慌てて失
言だったと謝る羽目になった。
風景な生活ぶりは、幾らクーパーでも簡単に推測出来た。しかもクーパーのする卑猥な与太話を笑って聞いてはいる
が、自らその話に便乗することは無いし、女性職員に対する下世話なジョークも苦笑するだけで黙って聞き流すのみ
だ。独身でこれほどの男が、何年も女っ気無しって言うのがどうにも解せず、ある日与太話のついでに、まさかホモじ
ゃあるまいなと問えば、恐ろしい顔で睨まれ、下らんことを言う暇があるなら仕事をしろと凄まれてしまい、慌てて失
言だったと謝る羽目になった。
クーパーは、小止みになってきた雨模様の夜空を、暢気な顔で見上げているドゲットの様子が腑に落ちなかった。
大抵の人間だったら落ち込んで飲んだくれるか、あるいは思い切って転職してしまいそうな、今回の己の処遇をこい
つは何とも思わないのか。しかもいくら今度の同僚だからって、女のことについて話すなど、前代見門だ。クーパーは
尚も探りを入れた。
大抵の人間だったら落ち込んで飲んだくれるか、あるいは思い切って転職してしまいそうな、今回の己の処遇をこい
つは何とも思わないのか。しかもいくら今度の同僚だからって、女のことについて話すなど、前代見門だ。クーパーは
尚も探りを入れた。
「大体あそこに配属されるってのは、お前、はっきり言って左遷だぞ。」
「そうなるかな。」
「今までのキャリアが全部不意になるかもしれないってのも、分かってんだろうな。」
「・・キャリアね。そうだな。」
「その割には、随分機嫌がいいな。」
「別に何時もと変わらん。」
機嫌がいいとクーパーに揶揄され、すかさず否定し渋面を作ったドゲットだが、その表情は何時もここに来る時の、重
苦しい雰囲気を伴うものとは、全く違うものだった。この時、ようやくクーパーはあることを悟り、瞠目してドゲットの顔を
見詰めた。
苦しい雰囲気を伴うものとは、全く違うものだった。この時、ようやくクーパーはあることを悟り、瞠目してドゲットの顔を
見詰めた。
「たまげたな。」
「何が?」
「お前さ。本当に平気なのか?」
「だから、何が。」
「だってありゃ、一筋縄じゃいかねえ女だぞ。しかも、お前の印象は最低だ。やっていけんのか?」
「別に。仕事をするだけだ。」
「あの女と仕事するんだぞ。抵抗は無いのか?」
「無い。」
もういい加減にしろと言う意味を込めて、ドゲットがきっぱりと言い切れば、その様子を眼を細め、ふうん、と言って眺
めたクーパーの続く言葉は、ドゲットを絶句させた。
めたクーパーの続く言葉は、ドゲットを絶句させた。
「そりゃお前、あのねえ・・じゃないスカリーが、美人だからそう言ってんのか?」
ドゲットは、顔を強張らせてクーパーをじろりと睨み、続いて信じられんというように疲れた溜息を付くとデスクに突っ伏
した。
した。
「まあ、確かに美人とだったら嫌われててもいいかもな。」
「何言ってんだ、お前は。」
突っ伏したままのくぐもったドゲットの声がしたが、クーパーは何処吹く風だ。
「それにあの薄暗い地下のオフィスで2人っきりだ。へへ、こりゃ堪らん。」
「何の話だ?」
「だってよ、密室で美人と2人っきりだぜ。仕事とはいえ美味しい話だ。まあ、性格はともかくありゃいい女だしな。」
「お前、いい加減に・・」
「じゃじゃ馬ほど、乗りこなし甲斐があるっていうじゃないか。俺の経験・・」
ばん、というデスクを叩く音が辺りに響き渡り、それは調子付いたクーパーを一瞬で黙らせた。思わず息を呑み盗み
見た視線の先に、ぴんと背筋を伸ばし平手でデスクを叩いた格好のまま、クーパーの方に向き直ったドゲットの姿が
あった。こりゃ本気で怒らせたなと、素早く悟ったクーパーは、もごもごと口籠りながら、ようやく謝罪の言葉を吐き出
した。
見た視線の先に、ぴんと背筋を伸ばし平手でデスクを叩いた格好のまま、クーパーの方に向き直ったドゲットの姿が
あった。こりゃ本気で怒らせたなと、素早く悟ったクーパーは、もごもごと口籠りながら、ようやく謝罪の言葉を吐き出
した。
「・・・・冗談だ。」
するとドゲットはむすっとした顔のまま、じろりとクーパーを睨み、デスクに肘を突き両手を組むとその上に顎を乗せ、
不機嫌に黙り込んでしまった。気まずい沈黙が流れ、間が持たなくなったクーパーは、慎重に言葉を選んで会話を再
開させようと試みた。
不機嫌に黙り込んでしまった。気まずい沈黙が流れ、間が持たなくなったクーパーは、慎重に言葉を選んで会話を再
開させようと試みた。
「・・ええっと、じゃあもう移動は終わったのか?」
ドゲットはちらりとクーパーを見たが、何も言わず同じ姿勢のまま、黙って小さく頷いた。ドゲットから反応が返ってきた
事に気を良くしたクーパーは、さらに尋ねる。
事に気を良くしたクーパーは、さらに尋ねる。
「そうか。・・・で、もう一緒に仕事してるのか?」
「いや。」
「そこまで嫌われてるのか?」
大仰なクーパーの言い方は、ドゲットの苦笑を引き出した。ドゲットがしょうがないなという風情で、肩を落とし溜息混
じりに行った口調は、穏やかだった。
じりに行った口調は、穏やかだった。
「それは知らんが、今彼女はアリゾナの病院に入院中で、仕事は無理だ。」
「病院?ああ、そうか。怪我をしたんだったな。重症なのか?」
「いや。今日報告に行った時は、元気そうだった。精密検査が長引いてる。」
「・・・ふうん。で、どうだった?」
「何が?」
「だから、ねえちゃんの反応さ。おっと、スカリーだったな。お前が配属されたって聞いて、どんな風だった?」
ドゲットはちょっと考えて、再び両手の上に顎を乗せ眼を少し伏せた。
「ショックを受けてたな。」
「・・・・やっぱり、そうだろう。で、お前どうしたんだ?」
「何が?」
「だーかーら、慰めるとか元気付けるとか、したんだろ?」
「いや。報告だけして帰ってきた。」
「何だそりゃ。お前、スカリーと上手くやってこうって気があるのか?」
「勿論ある。」
「じゃあ、何でそこで優しい言葉をかけてやらねえんだ。」
「必要ないからだ。」
「はあ?必要ない?・・・・・ははあ、そうか。そう言うことか。納得だな。」
呆れたような仕草で盛んに頷くクーパーを、ドゲットは不思議そうな顔で見詰め、探るように眼を細めた。
「何の話だ?」
「お前の話さ。何だ。そうなのか。ふうん。」
「何を独りで納得してるんだ?」
「お前はそういう男なんだな。」
「いい加減にしろ。何のことを言ってるのか、さっぱり分からんぞ。話す気が無いなら、これ以上は・・」
不機嫌そうに話を打ち切ろうとするドゲットを、待てよ、と些かうろたえ気味に遮り、クーパーは大きく息を吸ってから、
堂々巡りの会話を進ませることにした。
堂々巡りの会話を進ませることにした。
「俺は常々、どうしてお前は女ッ気がさっぱりなのか疑問だった。だがこれではっきりした。お前って男は、女に冷た
い。いや、冷たすぎる。前々からあっさりした野郎だとは知っていたが、ここまでとは思わなかった。いいか、良く聞け
よ。確かにあっさりしてるのはいい。だがそれは男にだけだ。女にそいつをやったら、そりゃお前冷たい男と取られて
敬遠されても仕様がねえぞ。」
い。いや、冷たすぎる。前々からあっさりした野郎だとは知っていたが、ここまでとは思わなかった。いいか、良く聞け
よ。確かにあっさりしてるのはいい。だがそれは男にだけだ。女にそいつをやったら、そりゃお前冷たい男と取られて
敬遠されても仕様がねえぞ。」
「冷たいか?」
「当たり前だ。長年の相棒がいなくなるわ、みつからないわで怪我までして意気消沈してるところへ、捜索に失敗した
野郎のご登場だ。おまけにこいつのせいで見つからなかったと思ってる奴が、今度の自分の相棒だ。幾ら、じゃじゃ
馬でも相当堪えてるはずだ。なのにお前と来たら、只単に報告して帰ってきただぁ?神経を疑うぜ。しょげてる女がい
たら、こう優しく労わって、元気付けるようなこと言って、握手の一つでもするもんだ。普通は。」
野郎のご登場だ。おまけにこいつのせいで見つからなかったと思ってる奴が、今度の自分の相棒だ。幾ら、じゃじゃ
馬でも相当堪えてるはずだ。なのにお前と来たら、只単に報告して帰ってきただぁ?神経を疑うぜ。しょげてる女がい
たら、こう優しく労わって、元気付けるようなこと言って、握手の一つでもするもんだ。普通は。」
「そういうものなのか。」
「そういうものだ。」
「それも経験か?」
クーパーはぐっと詰まって、表情が固まってしまった。ついさっきドゲット相手に女と仕事することの最低さ加減を並べ
立てたばかりだ。しかも経理の女性職員のところへ毎回詰め所の燃料費のことで怒鳴り込みに行っている男が、今
言ったことを実践していたとは、とても言い難い。先ほどからクーパーはかなり言いたい放題であるのに、それを怒る
風でもなく淡々と聞いていたドゲットなのだが、やはりきっちりとお返しはする。眼を白黒させて、クーパーは果敢に巻
き返しを計った。
立てたばかりだ。しかも経理の女性職員のところへ毎回詰め所の燃料費のことで怒鳴り込みに行っている男が、今
言ったことを実践していたとは、とても言い難い。先ほどからクーパーはかなり言いたい放題であるのに、それを怒る
風でもなく淡々と聞いていたドゲットなのだが、やはりきっちりとお返しはする。眼を白黒させて、クーパーは果敢に巻
き返しを計った。
「お、俺のことは、いい。今はお前の話をしているんだ。」
「そうだったな。」
真面目腐って答えるドゲットの、口元が僅かに綻んでいる。目ざとくそれを認めたクーパーは、心の中で歯噛みした。
ええい、くそ。癪に障る野郎だ。しかし、引っ込みの付かなくなったクーパーは、無理やり先を続けた。
ええい、くそ。癪に障る野郎だ。しかし、引っ込みの付かなくなったクーパーは、無理やり先を続けた。
「つまり。・・・・ああ、ええっと。・・つまりだ。俺の言いたいのは、女と話す時はもう少し考えてからものを言えってこと
だ。」
だ。」
「考えているさ。」
「よく言うな。それなら、何で捜索中お前等あんなに険悪だったんだ?」
ドゲットはちらりとクーパーに視線を送って肩を竦める。
「水ぶっかけられたのはなんでだ?説明してみろ。」
それを聞いたドゲットは組んだ両手に額を当て、下を向いて苦笑いをしている。それを見てようやくドゲットをやり込め
たと、横柄な態度で腕を組みほくそえむクーパーに、ふっと顔を上げドゲットが言った。
たと、横柄な態度で腕を組みほくそえむクーパーに、ふっと顔を上げドゲットが言った。
「いいぜ。」
「何だと?説明出来るのか?」
「ああ。」
「言っとくが、今思いついたんじゃ無いだろうな。」
「違う。」
「・・・・分かった。じゃあ、説明して貰おうじゃねえか。」
胡散臭そうな眼差しでドゲットを眺めクーパーは答えれば、ドゲットは身体を起こし片肘をデスクに付く格好で向き直り
穏やかな口調で語り始めた。
穏やかな口調で語り始めた。
「例えば、これ以上無いというぐらい酷いことが自分の身に起こったとする。しかも、自分が成すべき事は山のように
あり、退くことが出来ない状況だとする。そんな時辛さを煽るような言葉を聞いたらやる気が出るか?」
あり、退くことが出来ない状況だとする。そんな時辛さを煽るような言葉を聞いたらやる気が出るか?」
「まさか。」
「そうだろう。じゃあ、心の支えを失って、ぐらぐらしている人間が、己を奮い立たせる一番強い感情は、何だと思う?」
「何ってそりゃあ、・・・なにくそって思うような感情じゃねえと、先には進めねえ。怒りとか、憎しみとか。そんなところ
だ。」
だ。」
「そうだ。嘆きや悲しみに囚われると、人間はそこに止まって先に進めなくなってしまう。慰めや労わりは大事かも知
らんが、それはそういう感情を倍増させるだけだ。そして今回スカリーは、そこに止まれない状況だった。」
らんが、それはそういう感情を倍増させるだけだ。そして今回スカリーは、そこに止まれない状況だった。」
クーパーは、はっとしてドゲットの顔を見詰めた。
「待てよ。それじゃ、お前わざと?」
「ああ。」
「水ぶっかけられるように仕向けたのも、そうなのか?」
すると、ふふと苦笑し首の後ろを擦りながらドゲットは答える。
「ああ、あれ。まさか水をかけられるとは予想してなかったが、あれで彼女は一気にやる気を起こした。何処の馬の骨
か分からん男に、好き勝手させる気など消し飛んだんだろう。」
か分からん男に、好き勝手させる気など消し飛んだんだろう。」
「だが、結果お前に何時もえらい剣幕で突っかかるわ、単独で動くわで、とても協力的とは言えない態度になったぞ。
却って捜査の妨げになったんじゃねえのか?」
却って捜査の妨げになったんじゃねえのか?」
「いや。それは違う。俺は彼女が何をどう考えどう動くか知る必要があった。何故ならこの事件は、何処か妙だったか
らだ。誰も全てを話そうとはしない。誰もが少しずつ何かを隠している。だが、彼女が感情をむき出しにしてくれたおか
げで、その辺のところが大分見えてきた。それがこの事件の全容を知る手がかりにも繋がるだろうと、推測したん
だ。」
らだ。誰も全てを話そうとはしない。誰もが少しずつ何かを隠している。だが、彼女が感情をむき出しにしてくれたおか
げで、その辺のところが大分見えてきた。それがこの事件の全容を知る手がかりにも繋がるだろうと、推測したん
だ。」
クーパーは聞きながら複雑な表情になっていった。
「じゃあ、お前は最初から、スカリーをわざと怒らせるように仕向けていたと言うんだな。」
「そうなるな。」
「その事を彼女は気付いていないんだろう。」
「勿論。俺はそんなへまはしない。」
「このまま自分が嫌われていてもか?」
「関係ない。」
「だけど、そうも言っちゃおれんだろう。今度から毎日、2人っきりで顔付き合わせて仕事すんだぞ。」
「そうだな。」
「じゃ、何で今日会った時にそれを言わねえんだ。」
「必要ないからだ。」
「又それか。そうだな、お前の説は認めてやってもいい。まあ、賛成出来るわけじゃないが、お前にも考えがあったっ
てことは良く分かった。だがな、もういいんじゃねえのか?」
てことは良く分かった。だがな、もういいんじゃねえのか?」
「何が?」
「だから何も、これ以上誤解されるような態度を、取らなくてもいいって言ってるんだ。今日だって見舞いがてら報告に
行ったんじゃねえのか?事件も粗方かたが付いて、お前は彼女を怒らせる必要も無いし、彼女もやっと自分の感情
に浸れる時が来たんだ。労いの言葉ぐらいかけてやっても、お互い損にはならんだろう。」
行ったんじゃねえのか?事件も粗方かたが付いて、お前は彼女を怒らせる必要も無いし、彼女もやっと自分の感情
に浸れる時が来たんだ。労いの言葉ぐらいかけてやっても、お互い損にはならんだろう。」
「じゃあ聞くが、お前だったら、気に食わない奴から、突然同情されるようなことを言われたら嬉しいか?」
「あぁ?嬉しいどころか言われた瞬間ぶん殴ってるぞ。」
「はは。お前らしいな。」
乾いた笑い声を上げて苦笑するドゲットを、クーパーはやるせなく見詰め、長い溜息を付いた。そして哀れむような目
つきで穴の開くほどドゲットの顔を眺めた。その様子に、ドゲットは顔を顰め尋ねた。
つきで穴の開くほどドゲットの顔を眺めた。その様子に、ドゲットは顔を顰め尋ねた。
「何だ。」
「お前って奴は、つくづく要領が悪く出来てるな。」
「大きなお世話だ。」
「まあ、そう言うな。だがな、いいのか?それで。お前ずっと誤解されっぱなしで、やり難く無いのか?」
「さあな。仕事をするだけだ。」
「仕事っつっても、相手は相変わらずの態度で復帰してくるぞ。いいのか?」
「別に構わん。」
「構わんって・・・。」
クーパーは平然と言ってのけるドゲットを、呆れたように眺め暫し絶句した。が、直ぐに気を取り直し先を続ける。
「俺は前々からお前って男は、感情ってやつがどこか欠落してるんじゃないかと疑っていたが、そうなのか?」
「感情?」
「そうだ。この先あんな風にいちいち噛み付かれるんだぞ。腹立たしいとか、口惜しいとか思うだろう、普通。そうした
ら、誤解を解いておくのが最善のはずだ。それをしないってことは、お前にはそういう感情がねえとしか思えんぞ。」
ら、誤解を解いておくのが最善のはずだ。それをしないってことは、お前にはそういう感情がねえとしか思えんぞ。」
ドゲットは再び両肘をデスクに着き、手を組むと厳しい顔でクーパーを見た。
「クーパー、お前何か勘違いしてないか。今回の事件で、一番精神的にダメージを受けたのは、スカリーだ。重要な
のは彼女であって、俺では無い。ここで俺の感情など、全く関係無いんだ。そこを履き違えるな。」
のは彼女であって、俺では無い。ここで俺の感情など、全く関係無いんだ。そこを履き違えるな。」
静かだが決然としたドゲットの口調に、クーパーは黙って頷くしか無かった。すると、ドゲットは窓の外を覗き込み、止
んだな、と呟き大きく伸びをした。何時しか雨が上がり、月が煌々と辺りを照らしている。話は終わったと立ち上がろう
としたドゲットを、既のところで引き止め座らせたクーパーは、最後に一つ、と言って慎重に切り出した。
んだな、と呟き大きく伸びをした。何時しか雨が上がり、月が煌々と辺りを照らしている。話は終わったと立ち上がろう
としたドゲットを、既のところで引き止め座らせたクーパーは、最後に一つ、と言って慎重に切り出した。
「何、大したことじゃねえんだ。だが、言っとくけど俺は真面目に聞いてるんだ。真面目だからな。聞いても絶対怒るん
じゃねえぞ。」
じゃねえぞ。」
「何だ。早く聞けよ。」
「怒らねえんだな。」
「聞かなきゃ分からん。」
「正直、そう聞こえても仕方ないがふざけてる訳じゃないんだ。それでも・・・」
「帰るぞ。」
うんざりとした顔で言い捨てて立ち上がろうとするドゲットを、待てよ、待ってくれと慌てて引き止め、渋々座ったドゲッ
トにクーパーは向き直った。神妙な顔付きになったクーパーを見て、自然とドゲットも同じような顔付きになる。すると
それを認めたクーパーが、頃はよしと意を決しこう言った。
トにクーパーは向き直った。神妙な顔付きになったクーパーを見て、自然とドゲットも同じような顔付きになる。すると
それを認めたクーパーが、頃はよしと意を決しこう言った。
「お前は、ダナ・スカリーを美人だと思うか?いや、勿論客観的に見ての話だ。どうなんだ?」
ドゲットは一瞬顔を顰めてクーパーを凝視した。が、次の瞬間ふっと視線を逸らし俯くと、腿の上に置いてあった両手
をゆっくりと開いた。視線を落としたまま何処か思いつめた表情で、ドゲットは両方の掌を見詰めていたが、やがてそ
の手を固く握り締めると、不意に顔を上げクーパーを見て目元を綻ばせ滲むような笑顔で言い放った。
をゆっくりと開いた。視線を落としたまま何処か思いつめた表情で、ドゲットは両方の掌を見詰めていたが、やがてそ
の手を固く握り締めると、不意に顔を上げクーパーを見て目元を綻ばせ滲むような笑顔で言い放った。
「お前なんかには、死んでも教えてやらん。」
その表情のギャップに唖然としているクーパーを尻目に立ち上がったドゲットは、そうやってあっという間に会話を終
了させ、さっさと詰め所を出て行ってしまった。
了させ、さっさと詰め所を出て行ってしまった。
ヘリポートを横切りエレベーターへと向かうドゲットの後姿を、クーパーは詰め所の窓越しに眺めていた。月明かりに
浮かび上がるドゲットの背中を見詰めていると、我知らず顔が綻んでしまう。クーパーは、無性に嬉しかった。厚い雲
の切れ間からドゲットの本当の姿が、ほんの少し垣間見れたような気がしたからだ。
浮かび上がるドゲットの背中を見詰めていると、我知らず顔が綻んでしまう。クーパーは、無性に嬉しかった。厚い雲
の切れ間からドゲットの本当の姿が、ほんの少し垣間見れたような気がしたからだ。
そしてもう一つ。クーパーはエレベーターに乗り込もうとするドゲットが、こちらに気付き片手を上げたのを見て、自分
も同じように手を上げ、心底羨ましそうな顔になると、誰に言うとも無く呟いた。
も同じように手を上げ、心底羨ましそうな顔になると、誰に言うとも無く呟いた。
「くそ。苛付く男だ。宝物でも見つけたようなツラしやがって。」
終
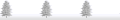
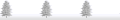
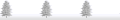
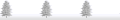
※後書き
この物語は「祝・クリス・クーパーGG賞最優秀助演男優賞受賞&アカデミー賞助演男優賞ノミネーション記念fic」です。パイロット、ケ
ネス・クーパーは彼がモデルです。以前からファンだった人の受賞に些か浮かれ気味に書きましたが、書き終わったら、結局ドゲットの
ことばっかりで、一体何処が「祝〜記念Fic」なんだと、愕然。
ネス・クーパーは彼がモデルです。以前からファンだった人の受賞に些か浮かれ気味に書きましたが、書き終わったら、結局ドゲットの
ことばっかりで、一体何処が「祝〜記念Fic」なんだと、愕然。
いや、こんなはずでは・・。クーパー、ごめん。
|
|

