

スカリーは最後の生徒の手当てをしてから、全員を医務室から追い出した。幸い酷い怪我の生徒はおらず、擦り傷
程度なのに大袈裟に手当てを求めて医務室に集まるのは、勿論町一番の美人の先生に優しく介抱されたいが為に
他ならない。バスケの練習試合中老朽化した観客席の支柱が折れるという、とんでもない事故だったが、何しろそこ
で応援していたのは全てこの高校の生徒ばかり。それも対戦相手の上品な都会の学生とは対極にあるような野生
児で、逃げ遅れて下敷きになるような輩は、1人もいない。
程度なのに大袈裟に手当てを求めて医務室に集まるのは、勿論町一番の美人の先生に優しく介抱されたいが為に
他ならない。バスケの練習試合中老朽化した観客席の支柱が折れるという、とんでもない事故だったが、何しろそこ
で応援していたのは全てこの高校の生徒ばかり。それも対戦相手の上品な都会の学生とは対極にあるような野生
児で、逃げ遅れて下敷きになるような輩は、1人もいない。
勿論試合は中止。一時その場は騒然となるも、崩れた観客席の側で呆然としている観客全てが、大した怪我をし
てないと確認するや、何事も無かったかのように試合を再開させるコーチに、今日はノーゲームにして、後日仕切りな
おしにするよう、真面目な副校長が説得したのだ。
てないと確認するや、何事も無かったかのように試合を再開させるコーチに、今日はノーゲームにして、後日仕切りな
おしにするよう、真面目な副校長が説得したのだ。
その後は、お定まりのパターンだ。擦り傷切り傷打撲傷、果ては小さなトゲが刺さったと、その場にいた学生達が、
大挙してその場に居合わせたスカリーを目指した。自分より遥かに身体の大きな男子高校生が、情けない顔で寄っ
てくるのを眺めていると、スカリーは毎度のことながら、動物園の飼育係になったようで、些かげんなりしてしまう。し
かしこれも仕事と割り切って、全員をぞろぞろと医務室に引き連れて行き、手早く処置を済ませ、終れば元気な者に
は用は無いと、さっさと追っ払った。
大挙してその場に居合わせたスカリーを目指した。自分より遥かに身体の大きな男子高校生が、情けない顔で寄っ
てくるのを眺めていると、スカリーは毎度のことながら、動物園の飼育係になったようで、些かげんなりしてしまう。し
かしこれも仕事と割り切って、全員をぞろぞろと医務室に引き連れて行き、手早く処置を済ませ、終れば元気な者に
は用は無いと、さっさと追っ払った。
「終ったの?」
戸棚に絆創膏やら傷薬をしまっていたスカリーは声のした方を振り返った。戸口には、既にシャワーと着替えを済ま
せ、こざっぱりした格好のコーチが立っている。このコーチ、運動神経もそこそこの化学教師だが、多才で殆どどんな
教科も教えることが出来、些か変わった趣味を持つが、それが却って親近感が湧くらしく、生徒には絶大な人気を誇
る。しかもルックス学歴と申し分ない為、町の独身女性の半分以上は彼に興味を持っている。時折起こす常識はず
れな行動も不思議と憎めない男だが、それが学校側、特に校長副校長の悩みの種であることに変わりは無い。
せ、こざっぱりした格好のコーチが立っている。このコーチ、運動神経もそこそこの化学教師だが、多才で殆どどんな
教科も教えることが出来、些か変わった趣味を持つが、それが却って親近感が湧くらしく、生徒には絶大な人気を誇
る。しかもルックス学歴と申し分ない為、町の独身女性の半分以上は彼に興味を持っている。時折起こす常識はず
れな行動も不思議と憎めない男だが、それが学校側、特に校長副校長の悩みの種であることに変わりは無い。
スカリーは去年赴任してからと言うもの、どういうわけか彼に気に入られ、何度かデートしたが、いまいち本気にな
れず、かといって彼女の知的レベルに適う相手もいないので、なんとなく付き合ってはいたが、恋人というには少し違
うと思っていた。それを向こうがどう思っているかは、別として。
れず、かといって彼女の知的レベルに適う相手もいないので、なんとなく付き合ってはいたが、恋人というには少し違
うと思っていた。それを向こうがどう思っているかは、別として。
「見れば分かるでしょう。ここを片付けたら校長に報告書を提出しなきゃ。」
「そんなの明日書いて、月曜に出せばいいだろう。今日はもう終わりにして、どう?食事でも。」
「校長がどうしても今日中と言って、待ってるのよ。そういうわけには行かないわ。あなたこそいいの?何もしないと管
理責任を問われるわよ。」
理責任を問われるわよ。」
「ああ、そりゃ大丈夫。体育館の管理責任者は、副校長だから、あいつに任せるさ。」
「副校長が?・・・・・ふーん、なんとなくそうなった理由が分かるわ。でも怪我人に関しては私が書くしかないし。」
「何人いるんだ?」
「57人。」
「そんなにいたのか。・・・・たいした怪我でもないのに、あいつらみんな君目当てだからな。でも校長は何だってそん
なに急がせるんだ?」
なに急がせるんだ?」
「明日理事会なの。その席で不利な立場に立ちたくないのよ。」
それを聞いて納得したコーチは、それでもぐずぐずとしつこく食事に誘ったが、仕事がはかどらず焦れたスカリーに、
冷たい眼差しで睨みつけられ、しょうがないなと、未練たらしそうな素振りで諦めた。
冷たい眼差しで睨みつけられ、しょうがないなと、未練たらしそうな素振りで諦めた。
「君と食事出来なけりゃ、午後は暇を持て余しちまう。」
「うそばっかり。あなたが暇そうにしてるところなんて、見たことが無いわ。それに明日は確か、例の3人組と砂漠の
調査に行くんじゃなかったの?」
調査に行くんじゃなかったの?」
「あっ!そうだよ。忘れるところだった。今夜は家でその打ち合わせだ。君も来るかい?」
「遠慮しとくわ。週末はゆっくり休みたいの。」
楽しいのに。と残念がるコーチだが、直ぐに今夜の下準備を思い出し、慌しく去っていった。コーチが出て行った後、
スカリーは小さく溜息を付いた。いい男だが、最近の我が物顔は癇に障るわ。まだあなたを恋人だと認めたわけじゃ
ないのよ。そこでスカリーはふと報告書を書く手を止めた。そう言えば、恋人にするのは申し分のない相手なのに、ど
うして私は踏ん切りがつかないんだろう。
スカリーは小さく溜息を付いた。いい男だが、最近の我が物顔は癇に障るわ。まだあなたを恋人だと認めたわけじゃ
ないのよ。そこでスカリーはふと報告書を書く手を止めた。そう言えば、恋人にするのは申し分のない相手なのに、ど
うして私は踏ん切りがつかないんだろう。
ややあってスカリーは首を振ると、肩を竦めた。別にどうだっていいわ。なるようにしかならないのよ。そう決まりをつ
け、コーチに関することを頭から振り払うと、校長の為にカルテを繰りながら報告書の作成に取り掛かった。
け、コーチに関することを頭から振り払うと、校長の為にカルテを繰りながら報告書の作成に取り掛かった。
スカリーが校長に報告書を提出して、帰宅しようと医務室を出たのは既に夕方になろうとしていた。ショルダーバッ
グを肩にかけ、玄関に向かう途中体育館の前を通りかかれば、中で何やら物音がする。崩れた観客席の撤去作業
は月曜日からと決まり、それまでは危険だから立ち入り禁止にしてあるはずだ。もしかしたら騒ぎを聞きつけた物見
高い生徒が、入り込んでいるのかもしれず、このまま見過ごして怪我でもされたら、又ひと悶着だ。
グを肩にかけ、玄関に向かう途中体育館の前を通りかかれば、中で何やら物音がする。崩れた観客席の撤去作業
は月曜日からと決まり、それまでは危険だから立ち入り禁止にしてあるはずだ。もしかしたら騒ぎを聞きつけた物見
高い生徒が、入り込んでいるのかもしれず、このまま見過ごして怪我でもされたら、又ひと悶着だ。
見つけたら一言叱り付け、直ぐに体育館から追い出そうと、おもむろに扉を開けたスカリーは、そこで見つけた光景
に思わず息を潜め立ち止まった。
に思わず息を潜め立ち止まった。
そこにいたのは、白いシャツにジーンズ姿の男子高生で、スカリーが見ているなど気付く風でもなく、黙々とバスケ
ットの用具を片付けている。彼女はそれが誰か直ぐに分かった。
ットの用具を片付けている。彼女はそれが誰か直ぐに分かった。
2年生の生徒だ。受け持ちのクラスを持たないスカリーが、医務室の常連でもない彼に興味を持ったのは理由があ
る。彼がある意味問題児なのは、赴任して程なく分かった。問題児といっても、素行や成績が悪いという、いわゆる
不良という意味ではない。成績も悪くはないし、友達に乱暴するとか、破壊的な行為や性質の悪い悪ふざけをするわ
けでもない。
る。彼がある意味問題児なのは、赴任して程なく分かった。問題児といっても、素行や成績が悪いという、いわゆる
不良という意味ではない。成績も悪くはないし、友達に乱暴するとか、破壊的な行為や性質の悪い悪ふざけをするわ
けでもない。
それならありふれた目立たない高校生かと言えば、それとも違う。まず一つは、彼は人目を引く、すっきりと整った
容姿をしていた。線の細いノーブルな顔立ちをしており、筋肉質な細身で、全体的に華奢な印象を受けるが、側に来
て初めて彼がすらりと背が高いと気付かされる。服装はTシャツにジーンズというありふれた格好しかしないのに、何
でもない着こなしに清潔感があり、誰しも好感を持つのは間違いないだろう。青年のそんな外見の中で、特に目を引
くのはその眼だった。青年は何時見ても思わずはっとする、綺麗な蒼い眼をしていた。
容姿をしていた。線の細いノーブルな顔立ちをしており、筋肉質な細身で、全体的に華奢な印象を受けるが、側に来
て初めて彼がすらりと背が高いと気付かされる。服装はTシャツにジーンズというありふれた格好しかしないのに、何
でもない着こなしに清潔感があり、誰しも好感を持つのは間違いないだろう。青年のそんな外見の中で、特に目を引
くのはその眼だった。青年は何時見ても思わずはっとする、綺麗な蒼い眼をしていた。
これだけの容姿の青年は中々都会でも見かけないが、田舎では更に稀だった。さぞかし町の女の子達にもてるだ
ろうと思いきや、まるでその気配は無い。確かにGFらしき女の子といるのを何度かみかけたが、どうやら熱を上げて
るのは女の方で、肝心の彼にはその半分もその熱心さはないのだ。おやおや。とその時スカリーは半ば呆れて見て
いたが、それも今では何となく分かる気がする。その訳は些か、彼が問題児と目されているところにも、関連があっ
た。一見して好青年としか見えない彼が、何故問題児なのかは、その極端に少ない出席日数と特異な性格に所以し
ているからだ。
ろうと思いきや、まるでその気配は無い。確かにGFらしき女の子といるのを何度かみかけたが、どうやら熱を上げて
るのは女の方で、肝心の彼にはその半分もその熱心さはないのだ。おやおや。とその時スカリーは半ば呆れて見て
いたが、それも今では何となく分かる気がする。その訳は些か、彼が問題児と目されているところにも、関連があっ
た。一見して好青年としか見えない彼が、何故問題児なのかは、その極端に少ない出席日数と特異な性格に所以し
ているからだ。
家庭の事情から何時も単位ぎりぎりの出席日数なのは、しょうがないとしても、限られた友達としか打ち解けて話そ
うとはせず、しかもその友達とさえあまり積極的に話をしているようには見えない。おまけに校長が出席日数のことで
呼び出し話をしても、最後に分かりましたと返事をするぐらいで、理由やいいわけなど一切口にしない。至極冷静な態
度で相手が一方的に話すのを黙って聞くのみなのだ。
うとはせず、しかもその友達とさえあまり積極的に話をしているようには見えない。おまけに校長が出席日数のことで
呼び出し話をしても、最後に分かりましたと返事をするぐらいで、理由やいいわけなど一切口にしない。至極冷静な態
度で相手が一方的に話すのを黙って聞くのみなのだ。
投げやりなわけでも、不遜な態度でも無い、青年の頑なまでに無口な性格には、教師達は勿論担任の歴史教師も
ほとほと手を焼き、既に匙を投げている。何時しか彼は、教師達の間で扱い難い生徒というレッテルを貼られ、とりあ
えず大人しいし、何か悶着を起こさない限り敢えて関わる必要も無いと、彼らの視界の隅に追いやられてしまったの
だ。
ほとほと手を焼き、既に匙を投げている。何時しか彼は、教師達の間で扱い難い生徒というレッテルを貼られ、とりあ
えず大人しいし、何か悶着を起こさない限り敢えて関わる必要も無いと、彼らの視界の隅に追いやられてしまったの
だ。
しかしスカリーは実はこの生徒が、檻に入れられるような類のシロモノではないと、随分前から気付いていた。どう
してみんな分からないのかしら。と、その時、ボールを拾い集めていた青年が、散らばるボールを眼で追った先に佇
むスカリーに気付いた。その途端、ばつの悪い顔で棒立ちになる。近づくスカリーの視線を避けるように、顔を背けた
青年は、むすっとした顔で作業を再開させた。スカリーは直ぐ近くに立つと、険のある口調にならないよう慎重に尋ね
た。
してみんな分からないのかしら。と、その時、ボールを拾い集めていた青年が、散らばるボールを眼で追った先に佇
むスカリーに気付いた。その途端、ばつの悪い顔で棒立ちになる。近づくスカリーの視線を避けるように、顔を背けた
青年は、むすっとした顔で作業を再開させた。スカリーは直ぐ近くに立つと、険のある口調にならないよう慎重に尋ね
た。
「何をしているの?」
彼はちらりとスカリーを見たが、見ればわかるだろうと言う素振りで、口を開かない。
「・・ああ、用具の片づけね。でもあなた、チームの一員でもないのに、何故こんなことを?」
ちょっと肩を竦めただけで、相変わらず何も答えないのでスカリーは足元のボールを拾い、つかつかと近づくと、屈ん
でボールを拾っている彼の鼻先に突き出し、何故なの?ともう一度尋ねた。すると青年は身体を起こし、差し出された
ボールを見て鼻先から垂れる汗を腕で拭い、所在無げに視線を彷徨わせていたが、渋々口を開いた。
でボールを拾っている彼の鼻先に突き出し、何故なの?ともう一度尋ねた。すると青年は身体を起こし、差し出された
ボールを見て鼻先から垂れる汗を腕で拭い、所在無げに視線を彷徨わせていたが、渋々口を開いた。
「ジーンが・・・。」
「ジーン?・・・・ああ、ジーン・クレインね。チームマネージャーの。彼は不運だったわね。肩を脱臼するなんて。さっ
き、お父さんが迎えに来ていたわ。そう、じゃあ、これはコーチに頼まれたの?」
き、お父さんが迎えに来ていたわ。そう、じゃあ、これはコーチに頼まれたの?」
途端に顔を強張らせ、横を向く。無理も無い。青年とコーチは犬猿の仲なのだ。聞くところによると、卓越した運動神
経の彼に眼をつけしつこくチームに誘ったコーチを、けんもほろろに断ったらしく、それがいたく自信過剰のコーチの自
尊心を傷つけたらしい。それ以来彼らの間にはしこりが残り、今ではすれ違っても挨拶どころか眼も合わせない。従っ
てコーチが彼に頼むなどありえないのだ。勿論スカリーだってそんなことは承知の上だった。
経の彼に眼をつけしつこくチームに誘ったコーチを、けんもほろろに断ったらしく、それがいたく自信過剰のコーチの自
尊心を傷つけたらしい。それ以来彼らの間にはしこりが残り、今ではすれ違っても挨拶どころか眼も合わせない。従っ
てコーチが彼に頼むなどありえないのだ。勿論スカリーだってそんなことは承知の上だった。
「じゃあ、誰が頼んだの?チームのみんな?でも、全員医務室に直行でそんな暇無かったわ。手当てが終ったら直ぐ
に帰ってしまったし。」
に帰ってしまったし。」
スカリーはボールを抱きかかえたまま首を傾げて、不機嫌に眼を逸らす青年を見上げた。
「副校長?まさかね。立ち入り禁止にしたのは彼ですもの・・。」
「ジーンが・・・。」
ようやく口を開いたと思えば又それかと、スカリーは眉間に皺を寄せた。だがここが肝心なのだ。慎重に。
「ジーンなら大丈夫。10日もすれば元通りよ。彼が心配?」
そうじゃないです、と聞き取れないくらいの声で呟き、不意に青年はスカリーに向き直った。
「ジーンが気にしていたので。」
「何を?」
「医務室に連れて行く時、用具を心配してたから。」
「ああ、そうなの。ジーンに頼まれたのね。」
「・・・・別に、頼まれたわけじゃ・・・」
それを聞いたスカリーの顔が綻ぶのを見て、うっかり口を滑らしたと、急に極まりの悪い顔になった青年は、上目にス
カリーを見て手を差し出す。
カリーを見て手を差し出す。
「何?」
「ボールを・・。」
「え?・・あ、そうね。」
すっかりボールのことなど忘れていたスカリーは、慌ててて差し出された手にボールを渡した。すると彼は控えめな眼
差しでスカリーの顔を窺い、丁重に尋ねた。
差しでスカリーの顔を窺い、丁重に尋ねた。
「もういいですか?」
口調は丁寧だが、そこには一刻も早くその場を離れたいという気持ちがちらちらと見え隠れする。スカリーはどうして
も、頬が緩むのを抑えられない。どんな教師の前でも、少しも臆することの無い彼が、どう言うわけかスカリーには何
かの拍子に居心地の悪い顔で、そうなることが多かった。微笑むスカリーの顔から、眩しそうに眼を逸らす青年などお
構い無しに、スカリーは先を続けた。
も、頬が緩むのを抑えられない。どんな教師の前でも、少しも臆することの無い彼が、どう言うわけかスカリーには何
かの拍子に居心地の悪い顔で、そうなることが多かった。微笑むスカリーの顔から、眩しそうに眼を逸らす青年などお
構い無しに、スカリーは先を続けた。
「気持ちは分かるけど、ここは今立ち入り禁止なのよ。副校長に何か言われる前に出た方がいいわ。」
「今出ます。これで終わりですから。」
「そう。ならいいわ。」
スカリーはボールを全部回収し、移動用のボックスを用具室に押してゆく青年の後姿を見送った。スカリーは青年の
親友を想う行為に微笑ましくなる一方で、この状態をうっちゃらかし、のほほんと自分を食事に誘いに来たコーチを思
い浮かべ、腹立たしさに舌打ちした。大体こういう気配りは、本来だったらコーチがすべきなのだ。そうなのだ。押しが
強く、何処か配慮の足りないあの男の、こういうところが彼女の二の足を踏ませる原因だった。
親友を想う行為に微笑ましくなる一方で、この状態をうっちゃらかし、のほほんと自分を食事に誘いに来たコーチを思
い浮かべ、腹立たしさに舌打ちした。大体こういう気配りは、本来だったらコーチがすべきなのだ。そうなのだ。押しが
強く、何処か配慮の足りないあの男の、こういうところが彼女の二の足を踏ませる原因だった。
そんなことを考え青年が出てくるのを待ちながら、スカリーは崩れた客席を見て回っていた。程なくして、用具室から
出てきた青年は、隅に置いてあったリュックサックを肩にかけ、スカリーがまだそこにいるのを認めると、如何にも待た
せてしまったと言う顔で、面映そうに近づいてきた。
出てきた青年は、隅に置いてあったリュックサックを肩にかけ、スカリーがまだそこにいるのを認めると、如何にも待た
せてしまったと言う顔で、面映そうに近づいてきた。
「それで、何か破損した用具はあったの?」
「選手のベンチぐらいです。」
「じゃあ、ジーンが心配するほどでは無いわね。練習や試合には関係ないから。他には?」
「後は個人の持ち物なので・・。」
「個人のって。誰の?」
青年はちょっと下を向いて鼻の横を擦った。
「・・・コーチです。」
「コーチ!?どういうこと?彼の何が?」
険しい顔で見上げたスカリーを、青年は無表情に見返し、客席の残骸を移動し、少し離れたところで止まると黙って
ある一点を指さした。慌てて駆け寄るスカリーが、指し示す奥を覗き見れば、ベンチと客席に挟まった手持ちのホワイ
トボードが見えた。これを小脇にコーチが選手に激を飛ばしていたのをスカリーは覚えていた。しかしそれは、大して
高価なものではなく、近所のディスカウントショップで何時でも手に入る。成る程。これなら彼の態度も頷ける。別に持
ち主が気に入らないから、取り立てて言わなかったわけではないのだ。如何にも一本気なこの青年らしく、スカリーは
にっこりして立ち上がりかけたが、ひしゃげたホワイトボードの近くにきらりと光るものを眼に留め、再び元の姿勢にな
った。
ある一点を指さした。慌てて駆け寄るスカリーが、指し示す奥を覗き見れば、ベンチと客席に挟まった手持ちのホワイ
トボードが見えた。これを小脇にコーチが選手に激を飛ばしていたのをスカリーは覚えていた。しかしそれは、大して
高価なものではなく、近所のディスカウントショップで何時でも手に入る。成る程。これなら彼の態度も頷ける。別に持
ち主が気に入らないから、取り立てて言わなかったわけではないのだ。如何にも一本気なこの青年らしく、スカリーは
にっこりして立ち上がりかけたが、ひしゃげたホワイトボードの近くにきらりと光るものを眼に留め、再び元の姿勢にな
った。
「危ないですよ。スカリー先生。」
「平気よ。それより、あれ何かしら?」
スカリーに尋ねられ隣に膝を着いた青年は、奥を覗き込んではっとした顔でスカリーを見た。
「ジーンの時計です。」
そう言ってリュックを下ろし、隙間から腕を入れようとする。その真剣な態度にスカリーは尋ねた。
「大事なものなの?」
「お祖父さんの形見だと言ってました。・・嵌めてると良いことが起こるとかなんとか。・・・・くそ、届かないな。」
不意に青年はスカリーを肩越しに振り仰ぎ、すいませんと謝った。スカリーはその律儀な態度に笑いを噛み殺し答え
た。
た。
「見逃して上げるわ。それより私と交代して。」
「先生じゃ無理ですよ。」
「あら、失礼ね。無理かどうかやってみなけりゃ分からないわ。」
と、わざとスカリーが気分を害した声を出せば、青年はおろおろと何やら口篭り、困り果てた顔で俯いてしまう。スカリ
ーはそれを見てちょっと可哀相になり、直ぐさま明るく話しかけた。
ーはそれを見てちょっと可哀相になり、直ぐさま明るく話しかけた。
「いいからどきなさい。子供は素直に言うことを聞くものよ。黙って大人に任せるのね。」
青年は黙って場所を譲ったが、今のスカリーの言葉に非常に腹を立てた素振りだった。スカリーはくすりと笑い、少し
も気にすることなく、うずくまり隙間から手を差し込む。頭上から青年の心配そうな言葉がかかる。
も気にすることなく、うずくまり隙間から手を差し込む。頭上から青年の心配そうな言葉がかかる。
「そこ。ぐらついてますよ。」
「注意してるから、大丈夫。」
スカリーは答えて更に肩口まで腕を押し込んだ。後もう少し。だがそこで異変が起こった。スカリーの肩に押された残
骸が、それまで微妙に保っていた均衡を崩したのだ。崩壊に時間はかからなかった。
骸が、それまで微妙に保っていた均衡を崩したのだ。崩壊に時間はかからなかった。
「先生!」
鋭い叫びを耳にしたのと、自分が強い力で後ろに引っ張られるのは殆ど同時だった。もうもうと埃を巻き上げ、がらが
らと崩れる客席の残骸の直ぐ前で、スカリーは横倒しに倒れていた。倒れたまま呆然と崩れる様を見ていたスカリー
は、はっとして手を開いた。
らと崩れる客席の残骸の直ぐ前で、スカリーは横倒しに倒れていた。倒れたまま呆然と崩れる様を見ていたスカリー
は、はっとして手を開いた。
「良かった。」
「良かないです。」
直ぐ近くで声がしたので振り返れば、澄んだ蒼い眼が怒ったように自分を見ている。綺麗だわ。一瞬見とれたスカリ
ーは慌てて取り繕うように手の中の腕時計を見せた。
ーは慌てて取り繕うように手の中の腕時計を見せた。
「そんなことないわ。ほら、ちゃんと取れたでしょう。」
「何言ってんですか!?危うく下敷きになるとこだったじゃないですか!」
「でも、ならなかったわ。」
「当たり前です!」
「助けて貰って感謝してるわ。」
「止めて下さい。」
「あら、どうして?お礼を言っちゃいけないの?」
暫しの沈黙の後、返事を待つスカリーに無愛想に青年は言い返した。
「どうでもいいですけど、どいてくれませんか?」
スカリーは言われて初めて、自分が青年の身体の上に、ちゃっかり乗ったままだと気付いた。ごめんなさい、と言い
ながら慌てて立ち上がれば、やれやれやっと苦行から解放されたという風に、些か顔を赤くさせた青年はゆっくりと立
ち上がる。身体に白く着いた埃をぱたぱたと払ってから、リュックサックを肩にかけスカリーに一礼すれば、もう用は済
んだとばかりすたすたと出口に向かう。慌ててショルダーバッグを持ったスカリーは、その後を追った。
ながら慌てて立ち上がれば、やれやれやっと苦行から解放されたという風に、些か顔を赤くさせた青年はゆっくりと立
ち上がる。身体に白く着いた埃をぱたぱたと払ってから、リュックサックを肩にかけスカリーに一礼すれば、もう用は済
んだとばかりすたすたと出口に向かう。慌ててショルダーバッグを持ったスカリーは、その後を追った。
「ちょっと待って。」
「まだ何か。」
「これを届けて頂戴。」
青年は隣に並んだスカリーから、ジーンの腕時計を受け取ると、分かりましたと、素っ気無く頷いた。相変わらず怒っ
た顔でポケットに腕時計をしまう青年の態度に、遅れないよう必死に歩調を合わせながら思わずスカリーは尋ねた。
た顔でポケットに腕時計をしまう青年の態度に、遅れないよう必死に歩調を合わせながら思わずスカリーは尋ねた。
「怒っているの?」
「別に。」
「それで?とても機嫌が良さそうには見えないわ。」
「僕の機嫌なんか、どうでもいいじゃないですか。これは届けますから、もういいでしょう。」
突然スカリーは青年の前に立ちはだかると、きっぱりと言い放った。
「そうはいかないわ。あそこにあなたがいなかったら、私はきっと下敷きになっていた。それを思うとあなたにはどれだ
け感謝しても足りないくらいよ。確かに私の行動は軽率だったかもしれない。だからといって、何もあなたを怒らせたく
てしたわけじゃないわ。お互いに良かれと思ってとった行動で、結果としては上手くいったんじゃないかしら。それな
のにこんな風に、気まずくこの場を別れるのは、私は納得出来ないわ。一体何が気に入らないの?」
け感謝しても足りないくらいよ。確かに私の行動は軽率だったかもしれない。だからといって、何もあなたを怒らせたく
てしたわけじゃないわ。お互いに良かれと思ってとった行動で、結果としては上手くいったんじゃないかしら。それな
のにこんな風に、気まずくこの場を別れるのは、私は納得出来ないわ。一体何が気に入らないの?」
すっかり居直ったスカリーに怖いものなど無い。例え相手が猛獣でも、その剣幕にはひれ伏すだろう。この青年がい
かに鋭い爪と牙を隠し持っていても、それが何の役に立とうか。案の定、青年は返事に窮し眼を泳がせ、困惑した顔
でスカリーを上目に見た。スカリーは直ぐに助け舟を出した。
かに鋭い爪と牙を隠し持っていても、それが何の役に立とうか。案の定、青年は返事に窮し眼を泳がせ、困惑した顔
でスカリーを上目に見た。スカリーは直ぐに助け舟を出した。
「怒らないから、構わず言いなさい。」
すると再び青年はむっとした顔になり、そっぽを向く。答えようとしない青年に焦れたスカリーが、身体が触れ合うくら
い詰め寄って、何なの?と詰問すれば、観念したのか青年は顔を背けたまま腹立たしそうに呟いた。
い詰め寄って、何なの?と詰問すれば、観念したのか青年は顔を背けたまま腹立たしそうに呟いた。
「子供扱いは止めて下さい。僕は・・・。」
言いかけた青年は、さっと頬を紅潮させ、しまったと言う顔になると、唇を噛んでスカリーの脇から身を翻し、走り去っ
た。その後姿をあっけにとられ見詰めるスカリーの頬が、ほんのり色づいていたなど、本人は知る由もないだろう。だ
が、久しく味わったことの無い、暖かい感情が湧き上がり、スカリーは我知らず微笑んでいた。
た。その後姿をあっけにとられ見詰めるスカリーの頬が、ほんのり色づいていたなど、本人は知る由もないだろう。だ
が、久しく味わったことの無い、暖かい感情が湧き上がり、スカリーは我知らず微笑んでいた。

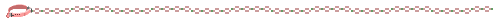
※後書き
なんと申しましょうか・・・。「canvas」を書いた後に、妄想が暴走しました。勢いで書いちまったもんですが、如何でしょうか。しかもこいつを
シリーズ化しようなどと、目論んでます。気楽に書いて息抜きたいんです。作者のワガママです。暫し付き合ってくださいましー。
シリーズ化しようなどと、目論んでます。気楽に書いて息抜きたいんです。作者のワガママです。暫し付き合ってくださいましー。
2003.8.21
|
|
|


