ドゲットはオフィスのデスクに置いた平たい小包を暫く眺めていた。差出人の名前も切手さえ貼り付けていないその
小包は、無味乾燥な茶色の包装紙に包まれ、厳重に麻紐で括ってある。出勤して直ぐに守衛に呼び止められ、中は
確認済みで危険物じゃ無かったからと、この小包を渡されたのだ。ドゲットは差出人に心当たりの無い、この平たく四
角い小包は一体何だと、首を捻った。
小包は、無味乾燥な茶色の包装紙に包まれ、厳重に麻紐で括ってある。出勤して直ぐに守衛に呼び止められ、中は
確認済みで危険物じゃ無かったからと、この小包を渡されたのだ。ドゲットは差出人に心当たりの無い、この平たく四
角い小包は一体何だと、首を捻った。
本。ややあってドゲットは、椅子にかけながらそう推理した。厚みといい大きさといい、何かの図録かアルバムと
か、そんな類の大きさだ。ドゲットはYシャツの袖を捲り上げ、とりあえず開けてみることにした。
か、そんな類の大きさだ。ドゲットはYシャツの袖を捲り上げ、とりあえず開けてみることにした。
麻紐に鋏を入れ、丁寧に包装紙を剥がす。現れたのは一冊の画集だった。ドゲットはケースの表紙を眺め画家の
名を確認し、微かに眉を顰め訝るような表情で、本体を引っ張り出すとゆっくりとページを繰り、暫しこの画家について
語った日に想いを馳せる。程なくページの合間から、おのずとこれを贈った差出人の顔が浮かび、ドゲットは眼を伏せ
仄かに微笑んで首を振った。覚えていたのか。
名を確認し、微かに眉を顰め訝るような表情で、本体を引っ張り出すとゆっくりとページを繰り、暫しこの画家について
語った日に想いを馳せる。程なくページの合間から、おのずとこれを贈った差出人の顔が浮かび、ドゲットは眼を伏せ
仄かに微笑んで首を振った。覚えていたのか。
その日はうららかな春の陽を感じさせる、気持ちの良い日だった。ドゲットはふと思い立ってスウェットの下をジーン
ズに履き替え、天敵にも等しい男が置いていった革のジャケットを肩に引っ掛け部屋を出た。明日の夜にはD.Cに帰
る。その前にもう一度訪れたい場所に行っておこうと思いついたのだ。ずっとベッドに縛り付けられ、退屈で気が狂い
そうだったし、幸い体調も良くなっているから、身体慣らしに歩くには丁度いいぐらいの距離にある。誰にも見つからな
いようこっそり建物を抜け出したドゲットは、久し振りの外気を胸一杯吸い込んで、林に分け入った。
ズに履き替え、天敵にも等しい男が置いていった革のジャケットを肩に引っ掛け部屋を出た。明日の夜にはD.Cに帰
る。その前にもう一度訪れたい場所に行っておこうと思いついたのだ。ずっとベッドに縛り付けられ、退屈で気が狂い
そうだったし、幸い体調も良くなっているから、身体慣らしに歩くには丁度いいぐらいの距離にある。誰にも見つからな
いようこっそり建物を抜け出したドゲットは、久し振りの外気を胸一杯吸い込んで、林に分け入った。
昼間見る湖は、又違った趣でドゲットを迎えた。鬱蒼と繁った木々も、その合間から真っ直ぐに湖に射し込む光も、
少しも変わらないはずなのに、光の強さとそれが織り成す色彩で、全く別の湖に見える。夜には墨を流したような湖
面も、今は陽光を反射しきらきらと輝き、鏡のような水面は湖をぐるりととりかこむ緑の林や青空を写し揺らめかせて
いる。
少しも変わらないはずなのに、光の強さとそれが織り成す色彩で、全く別の湖に見える。夜には墨を流したような湖
面も、今は陽光を反射しきらきらと輝き、鏡のような水面は湖をぐるりととりかこむ緑の林や青空を写し揺らめかせて
いる。
ドゲットはあの晩の岩の近くに、座るに手ごろな石を見つけ、腰を下ろした。屈む時脇腹と術後の傷痕が痛んだが、
そんなものはこの際無視するに限る。動けるようになればこっちのもの。口煩さではスカリーの上を行くジャニスに
は、さすがのドゲットもほとほと閉口していたからだ。
そんなものはこの際無視するに限る。動けるようになればこっちのもの。口煩さではスカリーの上を行くジャニスに
は、さすがのドゲットもほとほと閉口していたからだ。
ドゲットは膝に左肘を乗せ、折った腕を釣ったまま幾らかでも楽な姿勢を取ると、しんと静かな風景に暫し見入った。
鳥の囀りと岸辺に打ち寄せる水音だけがドゲットを包み、時さえ止まっているかのような錯覚を受ける。こんな風に彼
を取り巻く時間がゆったりと流れるのは久々で、そう言えばXーファイルに移ってから、自分はずっと走り詰めだった
と、改めて思い知らされた。
鳥の囀りと岸辺に打ち寄せる水音だけがドゲットを包み、時さえ止まっているかのような錯覚を受ける。こんな風に彼
を取り巻く時間がゆったりと流れるのは久々で、そう言えばXーファイルに移ってから、自分はずっと走り詰めだった
と、改めて思い知らされた。
ドゲットはふっと疲れた笑みを零し首を振った。違う。走り詰めだったのは、もっと前からだ。X−ファイルに移る前か
ら、次々と起こる凶悪事件をひたすら捜査し続けてきた。一つが解決すれば、直ぐに又別の事件が起こる。それは一
つの目標をクリアしても、直ぐ別の目標まで走らされるマラソンランナーにも似て、決して終らないレースを続けている
ようだ。只一つの違いは、走り始めた奴のペースを読まなければ自分は走れないという、分の悪い選択しか出来な
いことだろう。
ら、次々と起こる凶悪事件をひたすら捜査し続けてきた。一つが解決すれば、直ぐに又別の事件が起こる。それは一
つの目標をクリアしても、直ぐ別の目標まで走らされるマラソンランナーにも似て、決して終らないレースを続けている
ようだ。只一つの違いは、走り始めた奴のペースを読まなければ自分は走れないという、分の悪い選択しか出来な
いことだろう。
だがそうして脇目も振らず走り続ける生活を、ドゲットは何時も何処かで歓迎していた。この仕事を天職と誇りにして
いるし、情熱を傾けられる仕事に廻り合えた幸運に感謝もしている。何より間髪入れ無い出動頻度や膨大な仕事
量、常に緊張感漲る職種は、自分の性格にぴったりだと信じて疑わなかった。
いるし、情熱を傾けられる仕事に廻り合えた幸運に感謝もしている。何より間髪入れ無い出動頻度や膨大な仕事
量、常に緊張感漲る職種は、自分の性格にぴったりだと信じて疑わなかった。
都会の喧騒と仕事が無ければ生きてはいけないタイプの人間に、自分も当てはまるのだと、長年そう思っていた
が、こうやって人気の無い湖の岸辺に座り静寂に身を置いても、少しも手持ち無沙汰には感じない。確かにベッドに
縛り付けられるのは、飽き飽きしていたが、それは単に何もさせて貰え無いと言うだけで、ベンの地所にも彼の興味
の対象は無数にあるし、独り自然の只中で、静寂に心を委ねる術も心得ていた。
が、こうやって人気の無い湖の岸辺に座り静寂に身を置いても、少しも手持ち無沙汰には感じない。確かにベッドに
縛り付けられるのは、飽き飽きしていたが、それは単に何もさせて貰え無いと言うだけで、ベンの地所にも彼の興味
の対象は無数にあるし、独り自然の只中で、静寂に心を委ねる術も心得ていた。
考えてみれば、海兵隊を除隊してから都会での生活が長かった為、都市型人間であるかに錯覚しがちなドゲットだ
が、元々はジョージア出身なのだ。海兵隊に入隊するまでは、とても都会とは言い難い土地で育っている。そうやっ
てよくよく思い返せば、今までも気持ちを整理したい時など、必ず人のいない所を探していたような気がする。
が、元々はジョージア出身なのだ。海兵隊に入隊するまでは、とても都会とは言い難い土地で育っている。そうやっ
てよくよく思い返せば、今までも気持ちを整理したい時など、必ず人のいない所を探していたような気がする。
ドゲットは湖を眺めながら、ここに最初に来た時のことを思い出していた。あの晩、鹿の後を追ってここに辿り着い
た。だが今考えれば、何もそんなことをする必要は無かったのだ。危険など無いと、毎晩の見回りでとっくに分かって
いた。確かにこの場所は知らなかったが、それでも彼の五感全ては安全だと告げていた。
た。だが今考えれば、何もそんなことをする必要は無かったのだ。危険など無いと、毎晩の見回りでとっくに分かって
いた。確かにこの場所は知らなかったが、それでも彼の五感全ては安全だと告げていた。
なのにそそくさとあの場を離れたのには、訳があった。違うところで、警報が鳴ったのだ。境界線を超えるなと。だが
結局は、どういう気まぐれか後を追ってきたスカリーの為に、随分自分のことを喋らされたような、妙な具合になってし
まった。あの晩ここでの会話は何時もと違っていた。何処がどうと、はっきりとは言えないが、何かが変わった気がす
る。
結局は、どういう気まぐれか後を追ってきたスカリーの為に、随分自分のことを喋らされたような、妙な具合になってし
まった。あの晩ここでの会話は何時もと違っていた。何処がどうと、はっきりとは言えないが、何かが変わった気がす
る。
それが何だろうと考え込むドゲットの耳に、落ち葉を踏み分ける複数の音が微かに聞こえた。思考を中断し動かな
いまま耳を澄ませれば、まだ遠いその音の主が直ぐに判別出来た。犬と人。ここでは即ち、ベンと犬達だ。大方抜け
出したことがジャニスに知れて、探すよう頼まれでもしたのだろう。
いまま耳を澄ませれば、まだ遠いその音の主が直ぐに判別出来た。犬と人。ここでは即ち、ベンと犬達だ。大方抜け
出したことがジャニスに知れて、探すよう頼まれでもしたのだろう。
案の定、振り返った林の一角から、ドーベルマンが2頭躍り出て、ドゲットの姿を認めると、一目散に駆け寄ってく
る。ドゲットは苦笑しながら左腕を庇い身構えた。そうでもしなければ、殆ど体当たりに近い勢いで、ドゲットに圧し掛
かってくるであろうドーベルマンには、太刀打ちできない。骨を折ったなど、彼らには関係ないのだ。
る。ドゲットは苦笑しながら左腕を庇い身構えた。そうでもしなければ、殆ど体当たりに近い勢いで、ドゲットに圧し掛
かってくるであろうドーベルマンには、太刀打ちできない。骨を折ったなど、彼らには関係ないのだ。
ドゲットの予測どおり、飛び掛らんがばかりの勢いで、争って彼の顔を舐める2頭のドーベルマンを宥めていると、背
後から暢気そうな声がした。
後から暢気そうな声がした。
「パム、キム、離れろ。全く主人の制止も聞かずに飛び出すんだから。大した喜びようだな。」
ベンの言いつけを守り、素直にドゲットから離れた犬達は、そのまま辺りを散策し始め、濃紺のピーコートを纏ったベ
ンは、その姿を眼で追いながら、ドゲットの隣の手ごろな石に腰を下ろした。
ンは、その姿を眼で追いながら、ドゲットの隣の手ごろな石に腰を下ろした。
「悪かったな。あいつら加減を知らないから。傷が痛んだんじゃないか?」
「いや。平気だ。」
「ジャニスが心配してる。」
「そうだろうな。」
口ではそう言うものの、意に関せずといった風情のドゲットを、ベンは横目で見てしょうがないなと首を振り、まあ、い
いかと呟き、下を向いてにやにやしている。1人で何やら納得して笑うベンの様に、ドゲットは顔を顰めた。
いかと呟き、下を向いてにやにやしている。1人で何やら納得して笑うベンの様に、ドゲットは顔を顰めた。
「何だ?」
「え?」
「何が可笑しい?」
するとベンは慌てて片手で顔をつるりと撫ぜ、誤魔化そうとしたが、それでもまだ笑いを含んだ目つきでドゲットを見
た。
た。
「君みたいなタイプの奴が、今まで大人しくベッドにいたことさ。」
「俺みたいな?」
「典型的なワーカホリック。動ける限り仕事をしようとする、骨の髄までのFBI捜査官を見たのは、久し振りなんでね。
見舞いに行くたびに、退屈で死にそうな顔をしてたぞ。そんな君が今まで良く我慢してたな。」
見舞いに行くたびに、退屈で死にそうな顔をしてたぞ。そんな君が今まで良く我慢してたな。」
「当然だ。早く治さねば不味い事になる。」
ベンは下を向いて鼻を擦った。
「・・・・リオか。」
「そうだ。」
「なあに、心配しなくても大丈夫さ。あれでリオは僕なんかよりずっと要領がいい。散々渋ってはいたが、結構卒なくこ
なしているはずだ。」
なしているはずだ。」
余裕のある顔でそう告げるベンに、疑り深い視線を投げ横を向くドゲットを、ベンは複雑な顔で見詰めていたが、不意
に真顔になると慎重に口を切った。
に真顔になると慎重に口を切った。
「エージェント・スカリーが気になるんだね。」
「・・・・・・・え?あ、ああ、勿論。只でさえあの課は、上から目を付けられてるんだ。あいつの為に閉鎖に追い込まれ
でもしたら、今まで必死に課の存続に尽くしてきた彼女に、申し訳が立たん。」
でもしたら、今まで必死に課の存続に尽くしてきた彼女に、申し訳が立たん。」
予期してなかったベンの真面目な眼差しと口調に、何故か言い訳めいた口ぶりで答えたドゲットは、内心うろたえて
いる自分に驚いていた。その様子を面白がる風でも、冷やかす風でもない顔でじっと見ていたベンは、成る程、と呟
いてから、すっと視線を逸らし溜息の後に謎の言葉を呟き、唐突に話を変えた。
いる自分に驚いていた。その様子を面白がる風でも、冷やかす風でもない顔でじっと見ていたベンは、成る程、と呟
いてから、すっと視線を逸らし溜息の後に謎の言葉を呟き、唐突に話を変えた。
「・・・・・・・・・分かってないのは、相変わらずか。・・ところでこの湖。良く知ってたな。この場所に湖があることを知っ
ているのは、屋敷内でもごく僅かなんだ。最初に見つけた僕ですら、ここに移ってから3ヶ月経った後だったんだぜ。
どうやったんだ?僕が辞めてから、FBIの捜査法に新しいマニュアルでも出来たのかい?」
ているのは、屋敷内でもごく僅かなんだ。最初に見つけた僕ですら、ここに移ってから3ヶ月経った後だったんだぜ。
どうやったんだ?僕が辞めてから、FBIの捜査法に新しいマニュアルでも出来たのかい?」
ベンの台詞に思わず、まさか、と笑ってしまったドゲットは、話が逸れほっとしたという気の緩みもあってか、見つけた
時の経緯や、その時交わしたスカリーとの会話を、彼にしてはかなり余計に話していた。ベンは訥々とした口調で面
映そうに語るドゲットの話を、興味深げに聞いていたが、終わった時、極上の笑みを浮べ空を仰いだ。
時の経緯や、その時交わしたスカリーとの会話を、彼にしてはかなり余計に話していた。ベンは訥々とした口調で面
映そうに語るドゲットの話を、興味深げに聞いていたが、終わった時、極上の笑みを浮べ空を仰いだ。
「満月の晩か。君はラッキーだったな。」
「ラッキー?」
「ああ。この湖が一番美しく見えるのは、満月の晩だからさ。実際そうだっただろう?」
ドゲットはそう問いかけられ、脳裏に浮かんだ湖の情景に黙って頷いた。その顔をベンはちらりと見て、ふふと小さく
笑い声を漏らす。ドゲットは眼を細めベンの顔を眺めた。会った当初からの、何かを絶えず面白がっている風情のベン
の態度は、ドゲットの腑に落ちないことが多く、そこから劣悪な感情は窺えないものの、少なからず居心地の悪い思
いをさせられていたからだ。だがそんなドゲットなど、構うことなくベンは頬杖を付き、アーサー王ね、と呟いて再び愉
快そうな目つきで彼を見た。何となく冷やかされた気になり、むっとした顔で軽く睨めば、それを往なすような声でベン
は湖の中央を指差す。
笑い声を漏らす。ドゲットは眼を細めベンの顔を眺めた。会った当初からの、何かを絶えず面白がっている風情のベン
の態度は、ドゲットの腑に落ちないことが多く、そこから劣悪な感情は窺えないものの、少なからず居心地の悪い思
いをさせられていたからだ。だがそんなドゲットなど、構うことなくベンは頬杖を付き、アーサー王ね、と呟いて再び愉
快そうな目つきで彼を見た。何となく冷やかされた気になり、むっとした顔で軽く睨めば、それを往なすような声でベン
は湖の中央を指差す。
「あの辺の水の中から、剣を持つ腕が出て、獅子の顔の舳先の小船には鎧姿のアーサーがいる。」
ドゲットは僅かに眼を見晴らせ、直ぐには意味が飲み込めず、そうだ、と半信半疑で頷けば、にっこりとベンが笑いか
け答えを告げる。
け答えを告げる。
「ワイエス。」
「・・・そうだが。・・じゃあ・・」
「うん。母と最期に過ごした誕生日のプレゼントだったんだ。あの本だけは何があっても、手放さなかった。今でも隅か
ら隅まで覚えてる。物語も挿絵も素晴らしい本だ。」
ら隅まで覚えてる。物語も挿絵も素晴らしい本だ。」
そうしてベンは、彼方に視線を投げ、口を噤んだ。ドゲットは思い出に浸るかのように押し黙ったベンの、端正な横顔
を見詰め、暫し自分も少年の日に思いを馳せた。あの頃こんな大人に誰がなると予測していただろうか。自分の暮ら
す土地だけが、世界の全てで、その世界は、光と色彩と希望に満ちていた。だが何時の頃からか世界は色を失う。
自分がモノクロに彩られた世界の住人となって、どれだけの時間が流れたか、もうそれさえも考えなくなってしまっ
た。
を見詰め、暫し自分も少年の日に思いを馳せた。あの頃こんな大人に誰がなると予測していただろうか。自分の暮ら
す土地だけが、世界の全てで、その世界は、光と色彩と希望に満ちていた。だが何時の頃からか世界は色を失う。
自分がモノクロに彩られた世界の住人となって、どれだけの時間が流れたか、もうそれさえも考えなくなってしまっ
た。
不意に立ち上がったベンの動作に、ドゲットは我に返った。ベンはそのまま岸辺に近寄ると、足元の小石を拾い、湖
に向かって投げ始める。水切りだ。誰でも同じことをするもんだな。と、ドゲットは口元を綻ばせ、ベンの隣に歩み寄っ
た。ベンが数回石を投げ込むさまを黙って見ていたドゲットだが、得意満面な顔で肩越しに振り返ったベンを平然と見
返し、感想を述べてみせた。
に向かって投げ始める。水切りだ。誰でも同じことをするもんだな。と、ドゲットは口元を綻ばせ、ベンの隣に歩み寄っ
た。ベンが数回石を投げ込むさまを黙って見ていたドゲットだが、得意満面な顔で肩越しに振り返ったベンを平然と見
返し、感想を述べてみせた。
「まあまあだが、俺の方が上手い。」
聞いた途端、ベンはバランスを崩し、一回も水面を弾かず、どぼん、と音を立て沈んで行く小石と、ふふん、と鼻先で
笑うドゲットをかわるがわる見て、舌打ちをする。非難がましいベンの顔を、今度はドゲットが面白そうに眺める番だっ
た。
笑うドゲットをかわるがわる見て、舌打ちをする。非難がましいベンの顔を、今度はドゲットが面白そうに眺める番だっ
た。
「下手くそ。」
「はっ!そりゃ、どうも。でも、僕にそう言うからには、是非とも君の腕前を拝見したいね。」
「見せたいところだが、あいにくこれじゃあな。」
ドゲットは三角巾で釣った左腕を、ちょっと持ち上げ、さも残念だと首を振る。
「右で投げればいいじゃないか。」
「俺は左利きだ。」
「両方使えるように訓練してるんだろ?」
「銃だけだ。」
ベンは呆れ顔でドゲットの顔をじろじろ眺め呟いた。
「・・・・結構口が達者なんだな。・・・・・リオみたいだ。」
「何か言ったか?」
急に険しい顔で問い返したドゲットに、いや何も、と惚けたベンは手についた泥を払い、ジーンズの後ろポケットに手
を突っ込むと、湖の対岸でじゃれあっている犬達を眺めている。感慨深げなベンの表情に、ドゲットは何気なく言葉を
かけた。
を突っ込むと、湖の対岸でじゃれあっている犬達を眺めている。感慨深げなベンの表情に、ドゲットは何気なく言葉を
かけた。
「名残惜しいか?」
ベンはさっとドゲットに視線を投げ、聡い男だな、と薄く笑う。
「そりゃあね。無から皆で作り上げた場所だ。愛着がある。けれどこの国には、僕らの安住の地は無いんだ。前から
分かっていたことさ。その為の準備も随分前からしていたんだ。只、今回のことでそれが早まっただけだ。」
分かっていたことさ。その為の準備も随分前からしていたんだ。只、今回のことでそれが早まっただけだ。」
それを聞いて沈痛な表情で俯くドゲットの心を見透かすように、ベンは先を続けた。
「そんな顔するなよ。君達のせいなんかじゃない。君達は最善を尽くした。首尾も上々だった。いや、むしろ君達がい
なければもっと悪い方向に進んでいただろう。後は誰かが僕の背中を押せば、良かったんだ。でも身内じゃそれが出
来なかったのさ。みんなここが好きだからね。本音を言えば誰も移りたくは無いんだよ。まあ、君には悪いが、怪我人
が出て初めて皆が、いい潮時だと決心出来たんだ。君には感謝してるよ。」
なければもっと悪い方向に進んでいただろう。後は誰かが僕の背中を押せば、良かったんだ。でも身内じゃそれが出
来なかったのさ。みんなここが好きだからね。本音を言えば誰も移りたくは無いんだよ。まあ、君には悪いが、怪我人
が出て初めて皆が、いい潮時だと決心出来たんだ。君には感謝してるよ。」
ベンがほんの少し済まなそうな顔でドゲットの腕を見れば、予期せぬ謝罪と感謝の言葉に、面食らったような顔でド
ゲットは、いいんだ、それは、等と口篭る。ベンが照れ臭そうに顔を背けたドゲットを、実は会ったその日から好ましく
思っていたとはドゲットは知る由も無いだろう。ベンにとってドゲットは、自分がFBIにいた頃出会っていたら、もっと違う
人生を歩めたんじゃないだろうかと、そんなことを思わせる男だった。けれど出会った男は、顔かたちは瓜二つでも、
ドゲットとは正反対のリオだ。まあ、あれはあれで面白いがな。と、苦笑いを浮べれば、怪訝そうなドゲットの視線に
気付き、慌てて真面目な顔を作り、何でもない、と首を振る。ドゲットは、そうか、と気にする風でもなく、舞い戻ってじ
ゃれ付く犬達の相手をし始めた。
ゲットは、いいんだ、それは、等と口篭る。ベンが照れ臭そうに顔を背けたドゲットを、実は会ったその日から好ましく
思っていたとはドゲットは知る由も無いだろう。ベンにとってドゲットは、自分がFBIにいた頃出会っていたら、もっと違う
人生を歩めたんじゃないだろうかと、そんなことを思わせる男だった。けれど出会った男は、顔かたちは瓜二つでも、
ドゲットとは正反対のリオだ。まあ、あれはあれで面白いがな。と、苦笑いを浮べれば、怪訝そうなドゲットの視線に
気付き、慌てて真面目な顔を作り、何でもない、と首を振る。ドゲットは、そうか、と気にする風でもなく、舞い戻ってじ
ゃれ付く犬達の相手をし始めた。
あっさりしてるな。ベンは小さく溜息を付いた。他のことには非常に気がつくくせに、自分に向けられる感情には恐ろ
しく無頓着だ。鈍感とは少し違う。これじゃあ、リオがちょっかい出したくなるのも無理は無い。その時ベンはあること
を思いつき、にやりとほくそえんだ。彼もまた、リオ宜しくお節介をしたくなったのである。
しく無頓着だ。鈍感とは少し違う。これじゃあ、リオがちょっかい出したくなるのも無理は無い。その時ベンはあること
を思いつき、にやりとほくそえんだ。彼もまた、リオ宜しくお節介をしたくなったのである。
「さっき話した本の挿絵。あれを書いた挿絵画家の息子も、画家だって知ってたかい?」
「勿論。有名だ。」
「そう。絵を見たことは?」
ドゲットは首を振ると、足元の木切れを拾い遠くへ投げ、それを追い争い駆けて行く犬の後姿を眺めながら付け加え
た。
た。
「美術館は仕事で行くぐらいしか縁が無いが、残念ながら今までにそいつの絵は無かったな。」
「そうか。惜しいな。彼の絵は父親の遥か上を行く。見れば絶対君の気に入ると思うよ。」
「そうかい。だがあんまり前衛的なのは、勘弁して欲しいね。俺の頭では理解出来ん。」
ベンがふふと笑い、全然違うよ、と告げれば、安心したようにドゲットは頷く。それから2人は犬の後を追い、湖の岸辺
をそぞろ歩いた。ベンは微笑んだまま、その先を続ける。
をそぞろ歩いた。ベンは微笑んだまま、その先を続ける。
「彼については面白い話があるんだ。彼は非常に寡黙で多作な画家だ。田舎に引っ込んで只ひたすら創作に打ち込
む、いわゆる人間嫌いな画家であるらしい。だから彼が何をモチーフに描いているかなど、発表されるまで家族も知ら
ないことが多い。殆ど秘密主義に近いな。」
む、いわゆる人間嫌いな画家であるらしい。だから彼が何をモチーフに描いているかなど、発表されるまで家族も知ら
ないことが多い。殆ど秘密主義に近いな。」
「ふむ。だが画家って奴は仕上がる前の作品を、人に見せたがらないと聞くが・・。」
「勿論そうだ。でも彼の場合はもっと極端でね、大抵の画家は一作描き終わるまで見せないのが普通だろう。ところ
が彼の場合は同じモデルのシリーズ全部だったりするのさ。さて、ここからが本題だ。1986年、ある美術コレクター
が、彼の自宅に呼ばれる。コレクターは、彼が‘大きい個人コレクション’を見せたがっているとだけ知らされ、それが
どんな作品かは知らなかった。だが彼に名指しで呼ばれ、行かないコレクターはいないだろう。そこで見せられたの
が、‘ヘルガ’のシリーズだったんだ。」
が彼の場合は同じモデルのシリーズ全部だったりするのさ。さて、ここからが本題だ。1986年、ある美術コレクター
が、彼の自宅に呼ばれる。コレクターは、彼が‘大きい個人コレクション’を見せたがっているとだけ知らされ、それが
どんな作品かは知らなかった。だが彼に名指しで呼ばれ、行かないコレクターはいないだろう。そこで見せられたの
が、‘ヘルガ’のシリーズだったんだ。」
「ヘルガ?」
「そう。聞いたことは無いかい?確か1987年にD.Cのナショナル・ギャラリーでそのシリーズの展覧会があったはず
だし、同じ年に画集も出版されてる。随分話題になったんだが・・。」
だし、同じ年に画集も出版されてる。随分話題になったんだが・・。」
ドゲットは複雑な眼をして、微かに首を振った。
「知らんな。その頃はニューヨークだ。NYPD勤務だった。」
「ああ、そうだったね。いや、別に知らなくてもいいんだ。只、僕は幸運にもその展覧会に行ったんだが、そのシリーズ
を目の当たりにしてると、色々と考えさせられてさ。」
を目の当たりにしてると、色々と考えさせられてさ。」
ドゲットが眉間に皺を寄せ難しい顔になるのを認め、ベンは慌てて付け足した。
「あ、待て待て。警戒する必要はないぜ。僕は何も小難しい美術論を吹っかけようって、言うんじゃない。何しろ僕に
だって、絵の良し悪しなんて大して分かっちゃいない。好きか嫌いかが僕の判断基準だ。その基準で行くと彼の絵は
凄く僕好みなんだが、あのシリーズに関しちゃ、別格でね。」
だって、絵の良し悪しなんて大して分かっちゃいない。好きか嫌いかが僕の判断基準だ。その基準で行くと彼の絵は
凄く僕好みなんだが、あのシリーズに関しちゃ、別格でね。」
ベンは一旦言葉を切ると、湖の彼方に視線を投げた。
「彼は一つのモチーフを長い時間をかけ、非常にたくさんの作品を描く画家だ。その中で‘ヘルガ’のシリーズは、実
に15年の年月と240の作品に及ぶ。」
に15年の年月と240の作品に及ぶ。」
「・・・・15年で240か。そりゃ又・・。」
「うん。気の遠くなるような時間と、膨大な作品だ。でもまあ、その前のシリーズには、30年というのもあるから、彼の
作品群の中じゃ、抜きん出て長期間じゃ無い。けれどそのシリーズだけは、何故か考えずにはいられないんだ。」
作品群の中じゃ、抜きん出て長期間じゃ無い。けれどそのシリーズだけは、何故か考えずにはいられないんだ。」
「何を?」
「モデルになった‘ヘルガ’は、たまたまその時モチーフにしていた人物の世話に来ていた、近所の農婦だ。若くも無
ければ美人でもない。その彼女を、誰にも知られること無く、15年も描き続けてきた。彼が‘ヘルガ’という女をモデル
に絵を描いていることは、彼のワイフでさえ知らなかったんだ。15年だぜ。」
ければ美人でもない。その彼女を、誰にも知られること無く、15年も描き続けてきた。彼が‘ヘルガ’という女をモデル
に絵を描いていることは、彼のワイフでさえ知らなかったんだ。15年だぜ。」
ベンは信じられないと、首を振った。
「僕は凡人だから、芸術家の気持ちなんか理解出来ないが、それでもあの絵を見ていると、ついこう思ってしまう。彼
は‘ヘルガ’を愛していたんじゃないか、とね。画家とモデルの間柄を勘ぐるなんて、無粋なことだと充分承知してる
さ。けれど僕にはどうしても、彼らの間に何の感情も無かったとは思えないんだ。‘ヘルガ’は裸婦であったり着衣で
あったり様々だが、そのどれもが自然で、本当に普段の彼女の姿や、その時の気分を描き出している。確かにそれ
は彼が天才だからこそ成し得られたんだが、それだけで見る者にあれほど感銘を受けさせる作品を描けるものだろう
か。モデルを見詰め理解し、愛情を注ぐ。そうやって培われた情熱が作品に宿り、見るもの全ての心を打つのだと僕
は思う。・・・だが、それを15年だ。2人はその間、濃密な空間を共有していた。それは2人だけの、特殊な時間だった
はずだ。張り詰めた緊張感と、お互いを委ね合う安心感は、愛などと呼ぶには、あまりに崇高だったのかもしれない。
だから彼は15年間、秘密にした。僕のような俗物に、邪推されたくは無かったんだと、そう思えてならないんだ。」
は‘ヘルガ’を愛していたんじゃないか、とね。画家とモデルの間柄を勘ぐるなんて、無粋なことだと充分承知してる
さ。けれど僕にはどうしても、彼らの間に何の感情も無かったとは思えないんだ。‘ヘルガ’は裸婦であったり着衣で
あったり様々だが、そのどれもが自然で、本当に普段の彼女の姿や、その時の気分を描き出している。確かにそれ
は彼が天才だからこそ成し得られたんだが、それだけで見る者にあれほど感銘を受けさせる作品を描けるものだろう
か。モデルを見詰め理解し、愛情を注ぐ。そうやって培われた情熱が作品に宿り、見るもの全ての心を打つのだと僕
は思う。・・・だが、それを15年だ。2人はその間、濃密な空間を共有していた。それは2人だけの、特殊な時間だった
はずだ。張り詰めた緊張感と、お互いを委ね合う安心感は、愛などと呼ぶには、あまりに崇高だったのかもしれない。
だから彼は15年間、秘密にした。僕のような俗物に、邪推されたくは無かったんだと、そう思えてならないんだ。」
不意にベンは足を止め、ドゲットに向き直った。
「何も描かれていない、真っ白なカンバスに最初の一筆を下ろす時の、画家の心境を考えたことはあるかい?それに
続く一筆一筆に画家は一体何を込めるのかな。」
続く一筆一筆に画家は一体何を込めるのかな。」
半疑問形で途切れたベンの言葉に、ドゲットは返事に窮し眉間の皺を深くした。するとベンはふっと微笑み、再び歩き
始め、慌ててその後に続いたドゲットに、独り言にも似た口調で先を続ける。
始め、慌ててその後に続いたドゲットに、独り言にも似た口調で先を続ける。
「・・・・情熱。愛情。その時の心を映すのさ。どんなに秘密にしても、出来上がった作品は彼の心が描き出されてしま
う。」
う。」
突如くるりと振り返ったベンは、ドゲットの視線を真っ直ぐに捉え、何時に無く真剣な声を出した。
「襲撃の時、月虹が見えたそうだね。リオに聞いたよ。リオの話じゃ君は自分を、その一色しかない白い虹だと言った
らしいが、本当かい?」
らしいが、本当かい?」
話の矛先を突如振られ、些か面食らったドゲットだったが、その時の朦朧とした意識の中で話した記憶は確かに残っ
ている。展開が読めず顔を顰めながらも、事実なのでとりあえずドゲットが頷けば、ベンはすっと人指し指をドゲットの
胸に当て、低く囁いた。
ている。展開が読めず顔を顰めながらも、事実なのでとりあえずドゲットが頷けば、ベンはすっと人指し指をドゲットの
胸に当て、低く囁いた。
「君の胸に秘めたカンバスは、今のところ真っ白なんだろう。ちょうどあの夜の虹のように。けれどどんなに君が秘密
にしても、それは表れてしまう。この先色とりどりになった君の秘密のカンバスを最初に見るのは、誰なんだろうな。」
にしても、それは表れてしまう。この先色とりどりになった君の秘密のカンバスを最初に見るのは、誰なんだろうな。」
「・・・・言ってる意味が・・」
「分からないか?・・・・嘘だね。君には分かってるはずさ。」
ベンは確信に満ちた眼をして愉快そうに笑うと、煙に巻かれた顔で当惑げに立ち尽くすドゲットを促し歩き始めた。ド
ゲットがむすっとした顔で、ベンの言葉を胸で反復させていれば、話は終ったとばかりに、ベンは既に違うことを考え
ている。急に、あ、と声を上げ、ドゲットの腕に手をかけた。
ゲットがむすっとした顔で、ベンの言葉を胸で反復させていれば、話は終ったとばかりに、ベンは既に違うことを考え
ている。急に、あ、と声を上げ、ドゲットの腕に手をかけた。
「今、右手で投げなかったか?」
「そうだったかな。」
「いや、確かに投げたぞ。犬が追っていったじゃないか。右でも投げれるんだな。」
その後はしつこく右で水切りをやって見せろという、ベンとの押し問答になり、その話に関しては、二度と再び話題に
なることはなかったのだ。
なることはなかったのだ。
ドゲットは‘ヘルガ’と副題の付いた分厚い画集のページを繰り、その絵一つ一つに丁寧に眼を落とした。その素晴
らしい絵の数々は、ベンに解説されるまでも無くドゲットの胸に迫るものがある。そしてあの時は謎だったベンの言葉
の意味も、あれから経過した時と出来事全てが、ドゲットに答えを示している。
らしい絵の数々は、ベンに解説されるまでも無くドゲットの胸に迫るものがある。そしてあの時は謎だったベンの言葉
の意味も、あれから経過した時と出来事全てが、ドゲットに答えを示している。
「お早う、エージェント・ドゲット。」
ドゲットはその声に思わず立ち上がった。疚しいことなど何も無いのに、条件反射で目の前の画集を閉じ、怪訝そうな
目つきで歩み寄るスカリーの視線からさりげなく遠ざけようとしたが、上手くいってないことは、妙な顔つきに変わった
スカリーを見れば一目瞭然だ。如何にも取るに足らないものといった仕草で、机の上にあった報告書やら新聞やらで
画集を覆うが、ドゲットの態度の不自然さは隠しようが無かった。
目つきで歩み寄るスカリーの視線からさりげなく遠ざけようとしたが、上手くいってないことは、妙な顔つきに変わった
スカリーを見れば一目瞭然だ。如何にも取るに足らないものといった仕草で、机の上にあった報告書やら新聞やらで
画集を覆うが、ドゲットの態度の不自然さは隠しようが無かった。
何をうろたえているのだ。堂々としていればいいのだ。堂々と。思う心とは裏腹に、鼓動は早鐘のようで収まらな
い。どうかこのまま通り過ぎてくれ。ドゲットは平静を装いながら、今や机を挟んで前に立つスカリーに、ぎこちなく笑
いかけ、お早う、エージェント・スカリー、などと間の空き過ぎた挨拶を返してみる。スカリーはちらりと机の上に視線を
走らせ、続いて曖昧に微笑んだ。その笑顔は疑問を含んでおり、どうやらドゲットの望む展開には進みそうに無い。
い。どうかこのまま通り過ぎてくれ。ドゲットは平静を装いながら、今や机を挟んで前に立つスカリーに、ぎこちなく笑
いかけ、お早う、エージェント・スカリー、などと間の空き過ぎた挨拶を返してみる。スカリーはちらりと机の上に視線を
走らせ、続いて曖昧に微笑んだ。その笑顔は疑問を含んでおり、どうやらドゲットの望む展開には進みそうに無い。
「何を見ていたの?」
「いや。・・別に。」
「仕事に関するもの?」
「いいや。・・・その・・・・そういうものでは・・。」
スカリーは眉を顰めると、何時に無く歯切れの悪いドゲットの口ぶりに、不思議そうな顔で首を傾げる。
「私が見てはいけないもの?」
言いながらスカリーは、ゆっくりと机の周りを移動し、ドゲットの隣に近づく。全ての言動がスカリーの不信感を煽るだ
けに、身動き取れず立ち尽くすドゲットは、所在無く視線を泳がせ口篭るばかりだ。
けに、身動き取れず立ち尽くすドゲットは、所在無く視線を泳がせ口篭るばかりだ。
「あー・・それは、・・別にそういう・・」
「それとも、私に見られたら困るものなのかしら?」
「馬鹿な。・・・・そんなものじゃないよ。」
冷やかすようなスカリーの言い方は、まるでいかがわしいものでも見ていたかのように聞こえ、ドゲットは苦笑いして
否定したが、それを言ったスカリーは既にドゲットの直ぐ隣に立っている。
否定したが、それを言ったスカリーは既にドゲットの直ぐ隣に立っている。
「それなら構わないわけね。」
はっと気付けば、にっこりと笑ったスカリーは、驚くべき速さで報告書と新聞を払い除け、慌てて阻止しようと手を伸ば
したドゲットの鼻先から、傲然と画集を掠め取った。が、しかし自分の手にした物が、想像したものと些か趣が違った
のか、眼を見開いて穴の開くほど表紙を眺め、続いて隣のドゲットを振り仰ぐ。ドゲットは居たたまれなさに、もういい
だろうと、口を開きかけ返せと手を差し出した。
したドゲットの鼻先から、傲然と画集を掠め取った。が、しかし自分の手にした物が、想像したものと些か趣が違った
のか、眼を見開いて穴の開くほど表紙を眺め、続いて隣のドゲットを振り仰ぐ。ドゲットは居たたまれなさに、もういい
だろうと、口を開きかけ返せと手を差し出した。
ところがスカリーは、画集に眼を落としたまま、片手を上げドゲットの言動をきっぱりと一蹴し、そのまますとんと椅
子に腰掛け、一瞬表紙に見入っていたが、優雅な仕草で画集を開き、一枚一枚ゆっくりとページを繰る。側に立つド
ゲットは、取り上げる機会を窺い、話しかけようと身構えたが、煩そうな顔で一瞥され、簡単に意識の外に追いやられ
てしまった。
子に腰掛け、一瞬表紙に見入っていたが、優雅な仕草で画集を開き、一枚一枚ゆっくりとページを繰る。側に立つド
ゲットは、取り上げる機会を窺い、話しかけようと身構えたが、煩そうな顔で一瞥され、簡単に意識の外に追いやられ
てしまった。
既に画集に没頭し、他のことなど眼中に無いスカリーに、ドゲットはしょうがなく溜息を付いて、用が済んだら直ぐに
取り返そうと、そのまま机に凭れた。斜め下に眼を移せば、スカリーの赤い髪と滑らかな白い頬の線が見える。ドゲッ
トは小さな肩と、柔らかな髪の間から見える細いうなじを眺め、ページを繰るたび、仄かに漂うスカリーの香りに眩暈
を覚えた。
取り返そうと、そのまま机に凭れた。斜め下に眼を移せば、スカリーの赤い髪と滑らかな白い頬の線が見える。ドゲッ
トは小さな肩と、柔らかな髪の間から見える細いうなじを眺め、ページを繰るたび、仄かに漂うスカリーの香りに眩暈
を覚えた。
俺は何をそんなに動揺したんだ。ドゲットは心を落ち着けようと、スカリーの気配にも気づかないほど、心を捉えてい
た思考を省みた。そうだ。俺は画集を見ながら、あの日のベンの言葉を思い出していた。秘密の白いカンバス。成る
程、あの時の俺は白い虹で良かったのだ。
た思考を省みた。そうだ。俺は画集を見ながら、あの日のベンの言葉を思い出していた。秘密の白いカンバス。成る
程、あの時の俺は白い虹で良かったのだ。
仕事や生活では充実していても、世界に色は無かった。そしてそれを気にもしなかった。無用なものだと退け、見る
ことも存在自体も意識から遠ざけた。けれど境界線を作り、己を強く主張しないように心がけても、出来なかった。出
来るはずなどないのだ。
ことも存在自体も意識から遠ざけた。けれど境界線を作り、己を強く主張しないように心がけても、出来なかった。出
来るはずなどないのだ。
心の片隅の埋み火に、再び火を灯すきっかけが出来てから、世界が色づき始めるまで、時間はかからなかった。見
上げる深い海のような青。風に揺れ燃える赤。同時に見え出す、群青の湖や輝く満月、草萌える草原を渡る風の
音、かさこそと鳴る落ち葉とその枯れた色。
上げる深い海のような青。風に揺れ燃える赤。同時に見え出す、群青の湖や輝く満月、草萌える草原を渡る風の
音、かさこそと鳴る落ち葉とその枯れた色。
この世界を彩なす沢山のものに気付くたび、ドゲットは新鮮な驚きと、長い時間これらを無為に見過ごしてきたとい
う、一種後悔にも似た感覚に囚われ、相反する思いに身動きが取れなくなる。けれどそれは決して嫌なものではな
く、むしろそこにずっと浸っていたかった。心に灯った火は密やかに燃え、彼を照らし暖め和ませる。只彼はそれを守
り、眺めていたかったのだ。
う、一種後悔にも似た感覚に囚われ、相反する思いに身動きが取れなくなる。けれどそれは決して嫌なものではな
く、むしろそこにずっと浸っていたかった。心に灯った火は密やかに燃え、彼を照らし暖め和ませる。只彼はそれを守
り、眺めていたかったのだ。
俺のカンバスは、最早白くは無い。最初から白くなど無かったのだ。そうとも、全てを覆い隠そうと俺が白く塗ったの
だ。だがベンの言うとおり、どんなに秘密にしても表れてしまう。今では指先や視線、声の端々にまで溢れそうにな
る。息が触れ合うぐらい近くにいれば、引き寄せ身の内に閉じ込めたい衝動に駆られる。それを思うと俺のカンバス
は、さぞかし鮮やかに色づいていることだろう。
だ。だがベンの言うとおり、どんなに秘密にしても表れてしまう。今では指先や視線、声の端々にまで溢れそうにな
る。息が触れ合うぐらい近くにいれば、引き寄せ身の内に閉じ込めたい衝動に駆られる。それを思うと俺のカンバス
は、さぞかし鮮やかに色づいていることだろう。
ぱたん。と本の閉じられる音に、ドゲットは思わず息を止めた。ふと気付けば、スカリーが下からドゲットを見上げて
いる。ばつの悪い顔で、顔を背けるドゲットをスカリーは不思議そうに見た。スカリーはドゲットの狼狽ぶりが腑に落ち
なかった。これは人に隠れて見るような類のものではない。それなのに何故、卑猥な本を隠れて見ていた現場を押さ
えられた、子供のような素振りをするのだろう。
いる。ばつの悪い顔で、顔を背けるドゲットをスカリーは不思議そうに見た。スカリーはドゲットの狼狽ぶりが腑に落ち
なかった。これは人に隠れて見るような類のものではない。それなのに何故、卑猥な本を隠れて見ていた現場を押さ
えられた、子供のような素振りをするのだろう。
確かに画集には裸婦の絵も混ざって入るが、ドゲットがそういうものに下卑た反応を示すタイプではないと、とっくに
承知している。しかし逆にドゲットが、絵画や美術に深い憧憬があるわけでは無いということも、先刻承知の上だ。趣
味であるはずの無い高価な本を、何故どうしてドゲットは見ていたのだろう。しかもスカリーの眼を盗むようにしてだ。
スカリーは、顔を引き締めるのに苦労していた。
承知している。しかし逆にドゲットが、絵画や美術に深い憧憬があるわけでは無いということも、先刻承知の上だ。趣
味であるはずの無い高価な本を、何故どうしてドゲットは見ていたのだろう。しかもスカリーの眼を盗むようにしてだ。
スカリーは、顔を引き締めるのに苦労していた。
何故ならスカリーは、こんな風にうろたえるドゲットから何かを引き出すのが、大好きだったのだ。会話の先を読み
駆け引きをし、ドゲットの堅牢な鎧が綻んでいく様は、犯人を尋問し自白に追い込む時より、胸が高鳴った。普段がポ
ーカーフェイスなだけに、考えの読み取り難いドゲットの心の内側を覗く絶好の機会だし、そうして現れたものは、何
時も彼女を不思議な感動で満たした。従ってこうやって巡ってくる数少ない絶好の機会を、スカリーは逃す気も無いの
だ。
駆け引きをし、ドゲットの堅牢な鎧が綻んでいく様は、犯人を尋問し自白に追い込む時より、胸が高鳴った。普段がポ
ーカーフェイスなだけに、考えの読み取り難いドゲットの心の内側を覗く絶好の機会だし、そうして現れたものは、何
時も彼女を不思議な感動で満たした。従ってこうやって巡ってくる数少ない絶好の機会を、スカリーは逃す気も無いの
だ。
「それで、どうしたの?これは。」
スカリーは椅子の背に凭れ、顔を背けたまま言い淀んでいるドゲットを見上げた。ドゲットはさっと下に視線を向けた
が、スカリーが片手を本の上に置いたままなのを認め、苦い顔で再び横を向いた。くそ。あれでは取り上げることも出
来ない。さあな、としらばっくれればいいのだが、FBI捜査官宛に差出人不明の小包が送られているのに、それを黙っ
て見過ごすなど、却って不自然だ。かといって、正直に話せばその先の展開は、あまり考えたくない方向に進むかも
しれない。逡巡し答えられないドゲットなど構うことなくスカリーは、机の上の包装紙を広げ先を続ける。
が、スカリーが片手を本の上に置いたままなのを認め、苦い顔で再び横を向いた。くそ。あれでは取り上げることも出
来ない。さあな、としらばっくれればいいのだが、FBI捜査官宛に差出人不明の小包が送られているのに、それを黙っ
て見過ごすなど、却って不自然だ。かといって、正直に話せばその先の展開は、あまり考えたくない方向に進むかも
しれない。逡巡し答えられないドゲットなど構うことなくスカリーは、机の上の包装紙を広げ先を続ける。
「これで送ってきたのね。あなた宛だけど、差出人の名前が無いわ。」
「ああ・・うん。」
「調べたの?」
「・・・・いや。」
「事件に関係してるかも。鑑識に回した方がいいわ。」
「・・・その・・。」
と言いかけ、更に口の中で何事かを言うドゲットの言葉が聞き取れず、スカリーは苛立った声を出した。
「え?何ですって?」
「その必要は無い。」
「どう言う意味?差出人に心当たりがあるとでも?」
ドゲットは嫌な予感に渋い顔で、唇を噛んだ。スカリーはドゲットの顔を覗き込み、真っ直ぐに見上げて確認する。
「あるのね。」
ドゲットは眼を閉じ覚悟を決めた。ままよ。嘘は吐けない。
「誰なの?」
「・・・ベンだ。」
「ベン?・・・ベンって・・・あのベン・キャロウェイ?」
「そう。彼だ。」
「どうして彼だと分かるの?」
「・・・この話をしたのはベンだからだ。」
スカリーは、ふうん、と頷いたが、更なる疑問をぶつけてくる。
「そうだったの。でも何故これをあなた宛に?私達との接触は避けたいはずなのに、何故わざわざ送ってきたのかし
ら。ベンは単なるきまぐれで、こんなことをするような人じゃ無いわ。何か意味があるはずよ。」
ら。ベンは単なるきまぐれで、こんなことをするような人じゃ無いわ。何か意味があるはずよ。」
ドゲットは返事に窮した。エージェント・ドゲット。スカリーが改まった口調で名前を呼ぶ。こういう呼び方をするスカリー
から、逃れる方法をドゲットはまだ習得していない。何故これが送られてきたか理由が分かっているなら話して欲しい
と、理路整然と述べるスカリーの言葉を聞くうち、ドゲットは壁際に追い詰められた鼠のような心境になっていた。しか
もこういう時のスカリーは、ほんのりと頬を上気させ、見上げる青い瞳は星の如く煌き眩しいほどで、抗いがたい魅力
に心を惑わされる。
から、逃れる方法をドゲットはまだ習得していない。何故これが送られてきたか理由が分かっているなら話して欲しい
と、理路整然と述べるスカリーの言葉を聞くうち、ドゲットは壁際に追い詰められた鼠のような心境になっていた。しか
もこういう時のスカリーは、ほんのりと頬を上気させ、見上げる青い瞳は星の如く煌き眩しいほどで、抗いがたい魅力
に心を惑わされる。
突然ドゲットは限界だとばかりに降参した。何故なら、痺れを切らしたスカリーが立ち上がり、ドゲットの腕に軽く手
を沿え、顔が触れ合うくらいの距離から、まじまじとドゲットの瞳を覗き込んだからだ。話して、と囁くスカリーの声は甘
く、軽く触れているだけのスカリーの手の感触は、むき出しの腕から痺れるような幸福感を身体中に運んだ。気がつ
けば、あの時のベンとの会話の殆どを、スカリーに話していた。
を沿え、顔が触れ合うくらいの距離から、まじまじとドゲットの瞳を覗き込んだからだ。話して、と囁くスカリーの声は甘
く、軽く触れているだけのスカリーの手の感触は、むき出しの腕から痺れるような幸福感を身体中に運んだ。気がつ
けば、あの時のベンとの会話の殆どを、スカリーに話していた。
しかし僅かに残った理性が、既のところでベンと最後に交わした会話だけを省かせ、我に返ったドゲットはその事実
に、心の中で胸を撫で下ろす。危ないところだった。スカリーを目の前にして、それを口にするなど、そんな芸当は幾
らなんでも・・・・。ドゲットはじんわりと額に汗が浮かぶのを感じていた。
に、心の中で胸を撫で下ろす。危ないところだった。スカリーを目の前にして、それを口にするなど、そんな芸当は幾
らなんでも・・・・。ドゲットはじんわりと額に汗が浮かぶのを感じていた。
「そう。じゃあ2人とも同じ本を持っていたのね。」
「え?何?」
それまで黙って聞いていたスカリーの問いかけに、はっと現実に引き戻され、ドゲットは慌てて聞き返した。
「アーサー王よ。N・C・ワイエス挿絵の本だったんでしょう。奇遇ね。」
「あ、ああ。そうだな。」
「でもそれでよく分かったわ。何故この画集が送られてきたか。」
「そうか。」
「ええ。で、あなたはどう思ったの?」
「何が?」
スカリーは、顔を顰めると肩を落とした。今までの話は何だったの?と言わんがばかりにドゲットの顔を眺め、呆れ顔
で首を振る。
で首を振る。
「だから、彼らの関係よ。この2人はお互いをどう思っていたのかしら。あなたの意見が聞きたいわ。」
「さあ。・・・何とも言えんな。」
「どうして?中を全部見たんじゃないの?」
「そりゃ、見たさ。だが本人がそう言ったわけでも、直にそう言うのを聞いたわけでも無いしな。」
「じゃあ、ベンの説は的外れだと?」
「はっきり書いてあれば別だが、それが無い限り、僕にその判断は出来んよ。」
スカリーは一瞬穴の開くほどドゲットの顔を見詰め、続いて、ふふ、と含み笑いをする。
「あなたらしいわ。でも捜査をしてるんじゃないのよ。エージェント・ドゲット。これはあくまで感覚の問題なの。素直に
絵だけを見て。」
絵だけを見て。」
スカリーはそう言っておもむろに画集を開いた。ページを繰っては、どう?と小首を傾げ、ドゲットの顔を見る。言われ
るがままに絵を鑑賞するドゲットは、何と言葉を返していいものやら、ひたすら黙り込むしかない。何を企んでいるん
だ。
るがままに絵を鑑賞するドゲットは、何と言葉を返していいものやら、ひたすら黙り込むしかない。何を企んでいるん
だ。
「この絵から何も感じない?彼女のこの表情を見て、あなたは何も思わないの?」
スカリーが自分に何を言わせたがっているのか、とうの昔にドゲットには分かっていた。躊躇うことなど無い。言えば
いいのだ。たかが画家とモデルの話じゃないか。しかしドゲットにはそれがどうしても出来ない。何故ならベンの送っ
てきた画集を見た時から、画家とモデルの関係は、まるでそうなるのが当然の如く、別の人間2人の関係に移行して
いた。そうなった時それはあまりに切実で生々しく、そういった感情から長く遠ざかっていたドゲットが、移行している
人間の片割れを目の前にして、戸惑ってしまうのも止むを得ない。
いいのだ。たかが画家とモデルの話じゃないか。しかしドゲットにはそれがどうしても出来ない。何故ならベンの送っ
てきた画集を見た時から、画家とモデルの関係は、まるでそうなるのが当然の如く、別の人間2人の関係に移行して
いた。そうなった時それはあまりに切実で生々しく、そういった感情から長く遠ざかっていたドゲットが、移行している
人間の片割れを目の前にして、戸惑ってしまうのも止むを得ない。
するとそんなドゲットの心境を見透かすように、スカリーは柔らかく微笑み、俯いて静かに画集を閉じた。これで終わ
りかと、ほっとしかけたドゲットだったが、振り返ったスカリーが、つと身体を寄せたので、一瞬何事かと身構える。す
るとスカリーは、左胸のYシャツについた糸くずをそっと払った。ああ、何だ。そう安心しかけたドゲットに、追い討ちを
かけるようにスカリーは、掌を彼の心臓の真上に乗せたまま、すっとにじり寄りその耳元に唇を寄せ囁いた。
りかと、ほっとしかけたドゲットだったが、振り返ったスカリーが、つと身体を寄せたので、一瞬何事かと身構える。す
るとスカリーは、左胸のYシャツについた糸くずをそっと払った。ああ、何だ。そう安心しかけたドゲットに、追い討ちを
かけるようにスカリーは、掌を彼の心臓の真上に乗せたまま、すっとにじり寄りその耳元に唇を寄せ囁いた。
「言葉にせず秘めている方が、より強くここに響くものなのよ。エージェント・ドゲット。」
ほんの一瞬、熱い息をドゲットの耳に残し、スカリーは何事も無かったかのように元いた場所まで離れると、硬直し眼
を見開いたまま下を向くドゲットの顔をいたずらっぽく観察する。未だ事態が飲み込めず、やっとのことで息を吐き出し
瞬きを繰り返すドゲットの胸に手を押し付け、スカリーは心配そうな声を出した。
を見開いたまま下を向くドゲットの顔をいたずらっぽく観察する。未だ事態が飲み込めず、やっとのことで息を吐き出し
瞬きを繰り返すドゲットの胸に手を押し付け、スカリーは心配そうな声を出した。
「鼓動が早いわ。顔も赤いし、汗もかいてる。大丈夫?エージェント・ドゲット?」
誰のせいで、と恨めしい顔で何か言い返そうと顔を上げたドゲットだったが、再び近づいてくるスカリーの顔にぎょっと
して固まれば、こつんと額同士がぶつかった。大きな青い瞳が上目にドゲットの顔を見上げている。
して固まれば、こつんと額同士がぶつかった。大きな青い瞳が上目にドゲットの顔を見上げている。
「熱は無いわ。」
ドゲットはもうそれどころではない。息は早くなるし、喉はからからだ。続いて額を離したスカリーは、ごく自然な仕草
で片手をドゲットの額に当て、熱が無いか再確認をし、そのままするっと頬に手を滑らせ首筋に指先を這わせる。ドゲ
ットは思わずごくりと生唾を飲み、眼を閉じた。勘弁してくれ。
で片手をドゲットの額に当て、熱が無いか再確認をし、そのままするっと頬に手を滑らせ首筋に指先を這わせる。ドゲ
ットは思わずごくりと生唾を飲み、眼を閉じた。勘弁してくれ。
「・・・・でも、具合が悪いみたいね。これからカーシュに報告書の件で呼ばれているけど、あなたは行かない方がいい
わ。何だか今にも倒れそうよ。」
わ。何だか今にも倒れそうよ。」
その言葉が終る頃には、スカリーは既にドアのところまで来ていた。ようやく我に返り顔を上げたドゲットが口を開こう
とすれば、振り返ったスカリーは思わせぶりに微笑んだ。
とすれば、振り返ったスカリーは思わせぶりに微笑んだ。
「今日のところは私に任せて、あなたは絵でも見て、いい子にしていなさい。エージェント・ドゲット。」
如何にも当然と命令しスカリーが出て行くのを見届けたドゲットは、どさりと椅子にへたり込んだ。机に肘を着き両手
で顔を覆うと、長い溜息とともに、思わず声が漏れる。
で顔を覆うと、長い溜息とともに、思わず声が漏れる。
「参った。」
だがその肩は小刻みに揺れ始め、やがて喉の奥から押し殺した笑い声が漏れ出した。ドゲットは身体を起こすと、椅
子の背に凭れ笑いながら、画集に手を置き、再び参ったと呟き、片手で髪を梳く。あいつ、全て計算づくでここに送っ
たな。ドゲットは首の後ろを擦ると首を振った。
子の背に凭れ笑いながら、画集に手を置き、再び参ったと呟き、片手で髪を梳く。あいつ、全て計算づくでここに送っ
たな。ドゲットは首の後ろを擦ると首を振った。
ドゲットはひとしきり笑った後、今度は心静かに机の上にある画集の表紙を眺めてみれば、スカリーへは告げなか
った、一連の絵を見て感じた素朴な感想が再び蘇る。ドゲットはその絵に、孤独と再生の姿を見ていた。そしてその
時初めてドゲットは、何故ベンがこの画集のことを、彼に告げたか理解出来たのだ。
った、一連の絵を見て感じた素朴な感想が再び蘇る。ドゲットはその絵に、孤独と再生の姿を見ていた。そしてその
時初めてドゲットは、何故ベンがこの画集のことを、彼に告げたか理解出来たのだ。
2つのカンバスは、孤独で静謐で凛とした彩と再生の力を熱く秘め、重なり合う。笑いを含んだベンの、分かってる
はずさ、という声が遠くどこかでこだましていた。
はずさ、という声が遠くどこかでこだましていた。

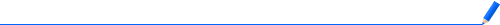
※後書き
カウントリク、初書きです。ぐらうちさんのリクは、映画「日の名残り」における、ミス・ケントンとミスター・スティーブンス、彼らの本を巡って
の攻防、その辺のイメージをアレンジして、しっとりした感じで。と、結構具体的であるような、無いような・・・・。でもって、このシーン、映画
の中でも、実は私のお気に入りのシーンでしたので、そりゃもう思いっきりパクりました。ホント、恥知らずな私。
の攻防、その辺のイメージをアレンジして、しっとりした感じで。と、結構具体的であるような、無いような・・・・。でもって、このシーン、映画
の中でも、実は私のお気に入りのシーンでしたので、そりゃもう思いっきりパクりました。ホント、恥知らずな私。
ええっと、何時に無く余裕のスカリーですが、この物語の時間軸は、「狼は還る」の後ぐらいと思って頂ければ、納得でしょうか。
ストーリーの中で話題に上る画家は、お気づきの方もいらっしゃると思いますが実在の人物で、アンドリュー・ワイエスのことです。問題の
画集、ワイエス画集 「ヘルガ」も実際に出版されていました。
画集、ワイエス画集 「ヘルガ」も実際に出版されていました。
さて、短編というリクエストにかなり苦心して短く纏めましたが、如何なものでしょうか。皆さんの感想お待ちしております。
2003.7.29
|
|

